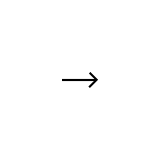230
周年事業を成功に導く"インナーブランディング"の力
周年を、ブランドの未来を描くプロジェクトに。
理念が息づく組織にづくりに向けた、インナーブランディングの重要性と実践ノウハウを伝授します。
1.なぜ「周年事業」にインナーブランディングが必要なのか
企業が創業から節目の年を迎えるとき、周年事業は単なる“記念イベント”ではなく、これまでの歩みを振り返り、これからの未来を社員とともに描くための経営の重要施策となります。しかし、周年事業を成功に導くうえで欠かせないのが、「社内への浸透=インナーブランディング」です。
外に向けた華やかな広報活動だけでは、真のブランド価値は育ちません。企業の本当の強さは、社員一人ひとりがブランドの理念に共感し、自らの言葉と行動で体現していくことによって築かれるからです。
この章では、周年事業が持つ本来の目的と、なぜ“内側からのブランドづくり”が成功のカギとなるのかを整理します。さらに、インナーブランディングが果たす役割と、社員のエンゲージメントが企業の未来をどう変えていくのかを紐解いていきます。

周年事業の本来の目的とは
企業にとって周年事業は、単なる「記念イベント」ではありません。創業〇周年という節目を迎えるこの機会は、これまでの歴史を振り返り、これからの未来を描く重要な“経営の転換点”です。
社外への感謝やブランド価値の訴求とともに、「自社の存在意義を再確認し、社員一人ひとりがその未来を共有する」ための時間でもあります。
つまり、周年事業の目的は「祝うこと」ではなく、「次のステージへ向かうために組織をひとつにすること」にあります。
「社外広報」だけでは成功しない理由
多くの企業が周年事業を実施する際、社外向けの広報活動(広告や記念イベント、ブランドキャンペーン)に力を入れがちです。もちろん、それらも大切な要素ですが、実は周年事業の成功を左右するのは「社内の共感と浸透」です。
社員が自社の歩みや価値に誇りを持ち、「この会社で働く意味」を再認識できるかどうかが、ブランドの持続的な成長につながります。
もし社員の理解や共感が不足したままでは、外向きのメッセージも一過性のものになり、せっかくの周年事業が「単なるイベントで終わる」リスクが高まります。
インナーブランディングが果たす役割
インナーブランディングとは、社員の意識や行動を企業理念・ブランド価値と一致させるための取り組みですが、周年事業においては次の3つの役割を果たします。
(1)理念の再浸透: 社史や創業ストーリーを通じて、企業の原点とビジョンを再確認できる。
(2)組織の一体感の醸成: 部署や世代を超えた交流・対話の機会を生み、挑戦意識を育てる。
(3)未来への共創意識: 経営層のメッセージと社員の想いを結びつけ、企業の未来を共に描く。
こうしたプロセスを経て初めて、周年事業は「過去を振り返る場」から「未来を創る起点」へと昇華します。
成功する周年事業の核心は「社員のエンゲージメント」
周年事業をきっかけに、社員が「自分たちのブランドをどう次世代へつないでいくか」を考えることができれば、それは企業文化の強化そのものです。
社外への発信よりも前に、社内での共感が生まれること。それこそが、周年事業を“意味ある節目”に変える最大の成功要因です。
2.インナーブランディングとは?周年事業との関係を整理

企業の節目となる周年は、単に創立を祝うためのイベントではなく、自社のブランドを内側から見つめ直す絶好の機会です。
市場環境や働き方が大きく変化する中で、社員が企業理念やブランドビジョンをどれだけ理解し、共感しているかが、これからの企業成長を左右する重要な要素となっています。その中核を担うのが「インナーブランディング」です。
インナーブランディングは、企業の“外”に向けた発信よりも、まず“内側”にブランドを根づかせ、社員一人ひとりが自らの言葉と行動でブランドを体現していくための取り組みです。
本章では、インナーブランディングの基本的な考え方と、それを推進するうえで周年事業がどのような役割を果たすのかを整理します。さらに、実際に成功している企業が得ている効果についても具体的に見ていきます。
インナーブランディングの定義と目的
インナーブランディングとは、社員が自社のブランドや理念を自分ごととして理解し、日々の行動を通じて体現していくための仕組みづくりです。単なるスローガン浸透ではなく、「企業の“らしさ”を社員が内側から育てていくプロセス」と言えます。
目的は明確で、組織全体が同じ価値観と方向性で動く状態をつくること。社員一人ひとりがブランドの担い手となり、企業文化として定着することで、社外に対しても一貫性あるブランド体験が生まれます。
アウターブランディングとの違い
ブランディングという言葉から、多くの人は広告やマーケティングなど“外に向けた活動”を思い浮かべます。しかし、アウターブランディングが「どう見られたいか」を設計するのに対し、インナーブランディングは「自分たちはどうありたいか」を明確にするプロセスです。
例えば、外部が広告やメディア露出を通じて顧客接点を築くのに対し、内部では理念共有会や社内ワークショップを通じて、社員の意識をブランドの方向へ整えることに重点を置きます。
言い換えれば、アウターブランディングは“発信”、インナーブランディングは“浸透”。どちらか一方ではなく、内側の理解が外の印象を支える「両輪の関係」が理想です。
周年事業がインナーブランディングの絶好の機会となる3つの理由
周年事業は、企業が自らの“これまで”を振り返り、“これから”の姿を社員と共に描き直す貴重な節目です。日常の業務では見落としがちな創業の原点や企業理念に立ち返り、改めて自社の存在意義を共有できる場でもあります。
(1)過去を共有することで、企業のストーリーに誇りを持つ機会となる
(2)未来の方向性を全社員で確認し、ビジョンを共通言語化できる
(3)部署や世代を超えたコミュニケーションが生まれ、組織の一体感が高まる
周年事業は、単に「祝う」ための行事ではありません。企業の価値を再構築し、社員の心にブランドを再び灯すための重要なプロセスなのです。
成功企業が周年事業で得る効果
実際に、周年事業をインナーブランディングの一環として戦略的に実施した企業では、次のようなポジティブな成果が数多く報告されています。
(1)理念の再定義と浸透
周年を機に企業理念やビジョンを改めて整理・共有することで、経営メッセージがより明確に伝わり、社員の理解と共感が深まります。
(2)エンゲージメントの向上
周年事業を通じて、社員同士や経営層との関係性が強化され、 「自分たちがこの会社をつくっている」という当事者意識と誇りが芽生えます。
(3)行動変化の促進
ブランドビジョンが具体的な行動指針として浸透し、社員の意思決定や日常業務に一貫性が生まれます。その結果、企業文化がより強固に育まれます。
(4)外部評価の向上
内側から生まれた自信と一体感が顧客対応やサービスの質に表れ、企業の信頼性やブランド価値の向上へとつながります。
周年事業は、一過性のイベントではなく、組織の意識を変え、文化を成長させるきっかけとなります。「内側の変化」が「外への評価」を生む。それこそが、成功企業が周年事業から得ている最大の成果です。
3.周年事業で実現するインナーブランディングの具体的効果

周年事業は、単なる節目のイベントではなく、組織の内側にポジティブな変化を起こす経営施策として大きな意義を持ちます。
社員一人ひとりの意識と行動が変化することで、組織全体のエネルギーが高まり、企業文化そのものが新たなステージへと進化します。
社員の一体感を高める「共感の場」
周年事業は、社員全員が共通の目的をもって参加できる貴重な機会です。世代や部署を超えた交流を通して、「自分たちは同じブランドを築く仲間である」という意識が生まれます。
その結果、社内に共感と信頼の連鎖が広がり、組織全体の一体感がより強固になります。
経営理念・ブランドビジョンの再確認
周年という節目は、企業の原点や存在意義を見つめ直す絶好のタイミングです。普段の業務では見えにくい「自分たちは何のために働くのか」という問いに立ち返ることで、社員は自社の理念やブランドビジョンを改めて理解し、自身の役割を再認識します。
このプロセスが経営メッセージと社員の想いを結びつけ、組織の方向性を再びひとつにします。
組織文化の再構築
周年事業は、過去を振り返るだけの行事ではなく、未来志向の企業文化を創り直すための機会でもあります。これまで培ってきた価値観や風土を継承しつつ、時代の変化に合わせて新しい働き方や企業の在り方を再定義する。
その積み重ねが、より柔軟で進化する企業文化の醸成につながります。
社員ロイヤルティの向上
自社の理念や歴史に共感し、誇りを持てるようになると、社員のロイヤルティは自然と高まります。この会社の一員であることに価値を感じる。そんな意識が、仕事へのモチベーションや主体性を高め、結果としてエンゲージメントの向上や離職防止にも寄与します。
4.成功する周年事業×インナーブランディング実践の5ステップ

周年事業を本当の意味で成功に導くためには、「イベントを実施すること」よりも、“どのように社員の共感とブランド浸透を生み出すか”が 最も重要なポイントです。ここでは、インナーブランディングの視点から見た、実践的な5つのステップをご紹介します。
【Step1】現状のブランド理解度を可視化する
最初のステップは、社員が自社のブランドや理念をどのように理解し、共感しているかを把握することです。アンケート、ヒアリング、ワークショップなどを通じて、「ブランドに対する意識のばらつき」や「共感度の現状」を見える化します。
現状を客観的に把握することで、どこに課題があり、どの層に浸透が足りていないかを明確にできます。“出発点を知ること”が、インナーブランディング成功の第一歩です。
【Step2】周年テーマ・コンセプトを設計する
次に、周年事業の目的を明確にし、それを象徴するテーマやメッセージを策定します。このコンセプトが、社内外へ一貫したメッセージを届けるための“軸”になります。
例えば
・「感謝と挑戦」:過去への感謝と未来への覚悟を込めて
・「つなぐ」:世代・拠点・価値を結び直す象徴として
企業理念やビジョンに基づいてテーマを設計することで、社員が「自分ごと」として捉えやすくなり、プロジェクト全体に統一感が生まれます。
【Step3】社員参加型の企画を取り入れる
周年事業の効果を高める要は、社員が主体的に関わる仕組みをつくることです。参加することで、社員は“自分も周年をつくる一員だ”という実感を得られます。
具体的な3つの取り組み例:
(1)社員代表によるプロジェクトチームの組成
(2)アイデアワークショップや社内公募による企画提案
(3)周年動画・展示・キャンペーンへの参加型制作
こうした関与が、社員のエンゲージメントを自然に高め、ブランドへの共感を深めるきっかけになります。
【Step4】記念誌や映像制作で理念を“見える化”する
周年事業を通して企業の歴史や理念を「形」として残すことは、ブランドの継承に大きな意味を持ちます。周年記念誌・周年・周年特設サイトなどのツールを活用し、企業の歩みと未来の方向性を可視化しましょう。
特に映像は、経営層の想いと社員の声を感情的に伝える強力なメディアです。社内外のプレゼンや採用活動など、周年後のさまざまな場面でも再利用できる“資産コンテンツ”になります。
【Step5】イベント後の継続施策を設計する
周年イベントが終わってからこそ、インナーブランディングの真価が問われます。社内報、オンライン共有会、ストーリーブックなどを通じて、周年で生まれた共感を継続的に育む仕組みをつくりましょう。
例えば
・社員インタビューやストーリーの連載
・社内SNSでの周年体験シェア
・ビジョンをテーマにしたワークショップ開催
周年を“ゴール”ではなく“スタート”と捉え、継続的な発信を行うことで、ブランド浸透が組織文化として定着します。
5.実践事例:周年事業を通じて変化した企業文化

周年事業は、単なる節目の行事ではなく、企業のDNAを再発見し、組織の未来を形づくるチャンスです。理念を見つめ直し、社員同士がつながり直すプロセスの中で、ブランドは内側から強く、しなやかに進化していきます。
ここでは、インナーブランディングの視点から周年事業を推進し、組織文化や社員意識の変革を実現した3つの企業の実践事例をご紹介します。
それぞれの企業が、“過去を語る周年”から“未来を共に描く周年”へとシフトすることで、理念の浸透、エンゲージメントの向上、そしてブランド価値の持続的成長を実現しています。
事例1:製造業|鎌ケ谷工業株式会社
創立50周年を機に「GO NEXT50 PROJECT!」を掲げた鎌ケ谷巧業。周年記念誌制作という当初の依頼から、「周年を次の50年を飛躍するきっかけにする」というブランド再構築へと発展しました。
まず全社員アンケートとトップインタビューを実施し、「揺るぎないプロフェッショナル集団であり続けたい」という姿勢をタグライン「まっすぐ、強く。」として明文化。ブランドムービー制作では、溶接や設計開発の現場を臨場感ある撮影により“巧の技”を強く表現。
さらに、記念誌やコーポレートサイト、ステーショナリーなどあらゆるコミュニケーションツールを刷新し、企業文化・理念・ブランドビジョンを社内外に一貫して浸透させました。
事例2:専門商社|シモダL&C株式会社
創業100周年を機に、シモダL&Cは“つなぎ、つくり、こたえる。”を掲げた3ヵ年計画のリブランディングを実施。全社員を巻き込んだアンケートとワークショップにより、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を策定。
そして、新社名「シモダL&C」に刷新し、ブランドムービーや周年サイト、コミュニケーションツールを一新。社員の「自分ごと化」を促進し、企業理念と日々の行動の連動を高めることで、社内浸透とブランド一致を実現しました。
事例3:製造業|ポーライト株式会社
創業70周年を迎えたポーライト株式会社は、社員とその家族への感謝を伝える周年事業を企画。「感謝と未来への決意」をテーマに、周年ロゴ・ブランドブック・記念バッジ・グッズを制作しました。
“成長・変化・チャンス”を象徴するロゴは未来への架け橋を表現。社員が誇りを持ち、家族が会社を語り合うきっかけとなる温かなブランド体験を実現しました。
6.成功のポイントと失敗しないための注意点

周年事業は、企業の節目を祝うだけでなく、ブランドを再構築し、社員の意識をひとつにする大切な経営プロジェクトです。しかし、その意義を十分に発揮するには、社内外の温度差をなくし、長期的な視点で取り組む設計が欠かせません。
ここでは、実践の際に押さえておきたい3つのポイントと、失敗を防ぐための注意点を整理します。
(1)経営層と現場の温度差をなくすコミュニケーション設計
周年事業では、経営層の想いと現場社員の受け止め方に温度差が生じやすいという課題があります。経営サイドが掲げるビジョンや理念を“伝える”だけではなく、社員がそれを自分ごととして理解し、共感できる形で届けることが重要です。
そのためには、
・経営層のメッセージを日常の業務や社内対話に落とし込む設計
・社員代表を巻き込んだ企画体制の構築
・双方向のコミュニケーションを意識した場づくり(対話会・ワークショップなど)
といった工夫が求められます。
「伝える」から「共有する」へ。コミュニケーション設計こそが、周年事業の成果を左右するポイントです。
(2)一過性で終わらせない仕組みづくり
多くの企業が陥りがちな失敗は、周年イベントを“その日限りの祝典”で終わらせてしまうことです。周年事業をブランドの成長機会とするには、イベントの後に何を残すかが重要になります。
例えば
・記念誌や映像を社内研修・採用活動などで活用する
・社内報やSNSで社員ストーリーを継続発信する
・ビジョン共有会や表彰制度などで理念を“行動化”する
といった、継続的に理念を体感できる仕組みを設けることで、周年事業の熱量を次のステージへとつなげることができます。
(3)外部パートナーの選び方が成果を左右する
周年事業を推進する際には、ブランディング会社や制作会社など、外部パートナーとの連携が欠かせません。ただし、単にイベントを“演出”するだけのパートナーではなく、企業理念や文化を理解し、共にブランド価値を高めてくれる存在を選ぶことが重要です。
選定時のチェックポイントとしては、
・企業の想いを丁寧にヒアリングし、理念に基づいた提案ができるか
・短期的な成果ではなく、長期的なブランド浸透を見据えているか
・他社の周年事例だけでなく、自社の課題に合わせた“設計力”があるか
を見極めることが大切です。
外部パートナーは“委託先”ではなく、“共創パートナー”として位置づける視点が成功のカギになります。
7.まとめ:周年事業を「次の100年への投資」にするために
周年事業は、過去を振り返るための儀式ではなく、「次の100年を共に創るための投資」です。インナーブランディングを軸に、社員一人ひとりが理念を共有し、行動へとつなげることで、組織は持続的に成長していきます。
いまこそ、周年をきっかけにブランドの未来を再設計し、企業文化を次世代へとつなぐ時です。私たちは、その想いを形にするパートナーとして、戦略設計から実行までをトータルに支援します。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《周年事業に関する記事一覧》
企業の節目を変わり目に!周年を契機とした企業ブランディングの最前線
周年は経営の転換点|ブランド再構築に活かす戦略的アプローチ
周年事業を成功に導く"インナーブランディング"の力
周年を機にMVV(ミッション/ビジョン/バリュー)を再浸透させる方法
周年ロゴとは?企業の節目を象徴するデザインとその役割
周年ロゴ制作の費用相場と制作期間|直依頼・代理店経由の違い
効果的な周年ツールとは?成功事例から紐解く5つのツール
成功する周年企画・ツール制作事例集
企業価値を高める周年ツール制作と費用プラン
周年ブランディングが得意なデザイン会社5選!
周年サイトで企業価値を高める!成功する構成とデザインを徹底解説
周年サイトに入れるべき10の必須コンテンツ
周年サイト制作の事前準備 完全ガイド
周年誌を外注する前に知っておきたい5つの基本
読まれる周年記念誌 完全ガイド|成果を出す構成・デザインのポイント
周年誌の企画アイデア集|"あゆみ"を感動に変える編集テーマ10選
周年記念誌のデザイン事例集|ブランドを象徴するビジュアル表現
周年動画とは?周年動画を制作する目的・メリット・成功事例を解説
社員参加型 周年動画の成功事例|社員主体でつくるブランディング動画
周年動画の制作方法|成功する企業アニバーサリームービーの作り方
企業向け周年動画 活用ガイド|目的別にわかる活用方法
周年オープニング動画の成功事例|感動と期待を生む構成ポイント
周年動画の制作費を徹底解説|企業規模別・用途別の費用相場
周年アイデア完全ガイド|周年事業・周年イベント企画の全手法
周年プロジェクト完全ガイド|進め方・事例・ツール制作まで徹底解説
周年事業を成功へと導くチェックリスト18項目