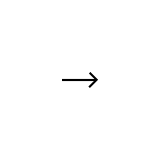195
SEO初心者必見!記事を書いても順位が上がらない原因と対処法
そのSEO、本当に効果が出ていますか?
今すぐすべき「SEO対策改善」の3ステップをご紹介します。
なんとなくのSEO対策から脱却する3ステップ
「とりあえず記事を書いているけれど、アクセスが伸びない」「キーワードは入れてるつもりだけど順位が上がらない」そんな悩みを抱える方は少なくありません。この記事では、“なんとなくやっているSEO”から脱却し、本質的な成果を出すためのコンテンツSEOの3ステップをわかりやすくご紹介します。

コンテンツSEOとは?
コンテンツSEOとは、ユーザーにとって価値のある「記事コンテンツ」を通じて、検索エンジンからの流入(アクセス)を増やす施策のことです。 単なるキーワードの詰め込みやテクニックではなく、「読者の悩みや疑問に答える良質なコンテンツを提供すること」に主眼を置いたSEO対策です。
Step1.正しいキーワードを選定する

キーワード選定の失敗は、そのまま検索上位への到達失敗につながります。さらに、ターゲットユーザーへのリーチを妨げ、最終的にサイト全体のパフォーマンスを大きく損なうリスクがあります。ここでは、よくあるNGパターンと、その解決策を詳しく解説します。
【NG】上位表示が難しいビックワードばかり狙う
ビッグワードは確かに検索ボリュームが多いため、魅力的に見えるかもしれません。しかしその裏には、膨大な競合サイトとの争いがあります。新規サイトや中小企業のサイトがこれらのキーワードで上位表示を目指すのは無謀とも言える状況です。結果、労力に見合った成果を得られないことが多くあります。
[上位表示が難しいビックワード例]
×「転職」×「化粧品」×「ダイエット」
【解決策】難易度と検索ボリュームのバランスを取る
SEOの基本は、「勝てる戦場で戦うこと」です。検索ボリュームはある程度ありつつ、競合が強すぎない、ミドルワードやロングテールキーワードを選定しましょう。
[勝つためのキーワード例]
×「転職」→ ◎「未経験 転職 成功例」
×「化粧品」→ ◎「敏感肌 スキンケア 化粧品」
×「ダイエット」→◎「ダイエット お腹 器具」
このように、自社の立場やユーザー層に合わせて現実的なキーワード選びを行うことで、10位以内へのランクインが狙いやすくなり、結果的に流入と成果につながります。
【NG】自社に合わないキーワードを選ぶ
いくら検索数が多いからといって、自社の提供価値と結びつかないキーワードを選ぶのは逆効果です。たとえ一時的にアクセスが増えても、ユーザーの期待と違う内容であれば、離脱率が上がり、SEO評価も下がってしまいます。
[自社に合わないキーワード例]
×英会話スクールなのに「韓国語 勉強法」で流入を狙う
×脱毛サロンなのに「美容 エステ」で流入を狙う
×飲食店のサイトなのに「ダイエット 食事制限」で流入を狙う
【解決策】自社サービスと親和性の高いキーワードを選ぶ
キーワード選定では、「そのキーワードで検索する人が本当に自社のサービスに興味を持つか?」を常に意識しましょう。ユーザーの検索意図と自社の強みが一致するキーワードを選ぶことが、継続的に価値ある流入を得る近道です。
[親和性の高いキーワード例]
英会話スクール →「英会話 マンツーマン 東京」
脱毛サロン → 「脱毛 全身 新宿」
飲食店 →「テイクアウト 渋谷 ランチ」
自社の提供価値に沿ったリアルな検索キーワードを拾い上げることが、最も効率の良いSEO対策です。
【NG】上位サイトの分析不足
検索結果で上位表示されているサイトには、上位にいる理由が必ず存在します。しかし日々の業務に追われて分析の時間が取れず、「なんとなく記事を書く」状態になっていませんか?これは非常に危険な状態です。
【解決策】上位10サイトのキーワードや構成を徹底分析する
まずは、狙いたいキーワードで実際に検索してみてください。そして上位10サイトを以下の4つの観点で分析します。
1.どんなタイトル・見出し構成か?
2.どんなユーザーの悩みを解決しているか?
3.使用している共起語や専門用語は?
4.記事の長さ、視認性、メディア要素(画像・動画)は?
上記リサーチを行い、上位サイトの共通点と差別化できるポイントを把握した上で、自社コンテンツに落とし込むことが重要です。
Step2.検索意図に合ったコンテンツ設計

キーワードをもとに記事を作成する際、ただ単に文章を量産するだけでは、検索上位には届きません。検索ユーザーが「なぜそのキーワードで検索したのか=検索意図」に寄り添ったコンテンツ設計を行うことで、SEO効果を最大化することができます。
【NG】キーワードを詰め込むだけの記事
例えば、「英会話 初心者」というキーワードをとにかく文中に繰り返すなど、SEO対策としてキーワードを多く盛り込もうとするあまり、不自然な文になったり、読み手にとって価値のない情報になってしまうケースがあります。検索エンジンも進化しており、単なるキーワード出現数では評価されません。
【解決策1】検索意図に応じた記事構成を設計する
例えば「英会話 初心者」というキーワードを検索する人は、「何から始めればいいのか?」「効果的な学習方法は?」「おすすめ教材は?」などの情報を求めていると推測できます。これを踏まえ、検索するユーザーの背景や悩みを想像し、その意図に答える内容を構成することが重要です。
【解決策2】検索意図に応じた記事構成を設計する
検索意図は「1.情報収集型」「2.比較検討型」「3.購入・行動型」の3段階に分けられます。それぞれの段階に合わせて記事内容や見出しを設計することで、ユーザーの満足度が高まり、離脱率を下げ、SEO効果も向上します。
1.情報収集型:例「○○とは?」で検索
2.比較検討型:例「○○ 比較 おすすめ」で検索
3.購入・行動型:例「○○ 申し込み」で検索
【解決策3】競合との差別化ポイントを明確にする
上位に表示されている記事と同じような内容では、ユーザーに選ばれにくくなります。そこで重要なのが「差別化」です。
・専門家の意見を取り入れる
・独自のデータや事例を提示する
・より詳しく、丁寧に解説する
このように、他の記事にはない“付加価値”を持たせることで、検索順位だけでなく、読者の信頼も獲得することができます。
【NG】見出しや構造がバラバラで読みにくい
どれだけ良い内容を書いていても、構造が整理されていない記事は、ユーザーにとって非常に読みにくく、SEO上もマイナス評価となります。
【解決策】段階的な検索意図に沿った構成に整える
ユーザーの検索行動は、「1.知りたい→2.比べたい→3.行動したい」という段階的な流れがあります。これに合わせ記事を次のように構成すると効果的です。
・導入:このキーワードで検索した人はどんな悩みを持っているか
・本論:悩みに対する具体的な解決策(比較・情報提供など)
・結論・行動:次にすべきこと、申込み、問い合わせ、などの行動喚起
さらに、見出しタグ(h2、h3など)を論理的に整理することで、検索エンジンにも正確に内容が伝わりやすくなります。
Step3.継続的な検証と改善

SEO対策(コンテンツSEO)は「記事を書いて終わり」ではありません。検索アルゴリズムは常に変化しており、ユーザーのニーズも日々移り変わります。だからこそ、継続的な分析と改善のサイクルを回すことが、安定した成果へと直結します。
【NG】記事を書いたら放置/アクセス解析を見ない
記事を公開した後、そのまま放置していませんか?また、Google AnalyticsやSearch Consoleなどのツールを設置しただけで、データを見ていないというケースも少なくありません。
これでは、どの記事が成果を上げていて、どの記事が改善の余地があるのかが分からず、SEO効果の最大化が難しくなります。
【解決策1】Google AnalyticsやSearch Consoleで定期チェック
Google Analyticsでは、ユーザー数、滞在時間、直帰率などを確認できます。またSearch Consoleでは、検索キーワード、クリック数、表示回数、平均掲載順位といった指標が取得できます。これらを定期的にチェックすることで、改善のヒントを得ることができます。
・どの記事が読まれているか
・どんなキーワードで流入しているか
・読者がどの段階で離脱しているか
【解決策2】順位変動を確認して内容をブラッシュアップ
記事は一度書いたら完成ではありません。公開後に検索順位の変動を確認し、上がらない記事は見出しや内容を見直す・追記するといったブラッシュアップが必要です。
特に、検索順位が10位〜20位あたりの記事は、少しの改善で1ページ目に入るチャンスがあります。情報の鮮度を保つことも重要です。
【解決策3】ABテストや追加コンテンツで効果測定
1つの表現にこだわらず、タイトルやCTA(行動喚起)を複数パターンで試すABテストも有効です。また、読者の反応や検索キーワードに応じて、関連する記事を追加で公開することも、SEO強化につながります。
改善を重ねていくことで、サイト全体の評価も高まり、検索順位や流入の安定化が期待できます。
まとめ:“なんとなく”から“戦略的”なSEOへ
「とりあえず記事を書く」「キーワードを入れておく」といった対策では、もはや検索上位を狙うことは難しい時代です。本記事でご紹介した3ステップを実践することで、SEOの本質を理解し、狙ったユーザーに確実に届くコンテンツを作ることが可能になります。
重要なのは、感覚や勘に頼るのではなく、データと検索意図に基づいた戦略的なアプローチに切り替えること。そして、地道な改善を重ねていくことが、長期的な成果と安定した検索順位を生み出します。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。