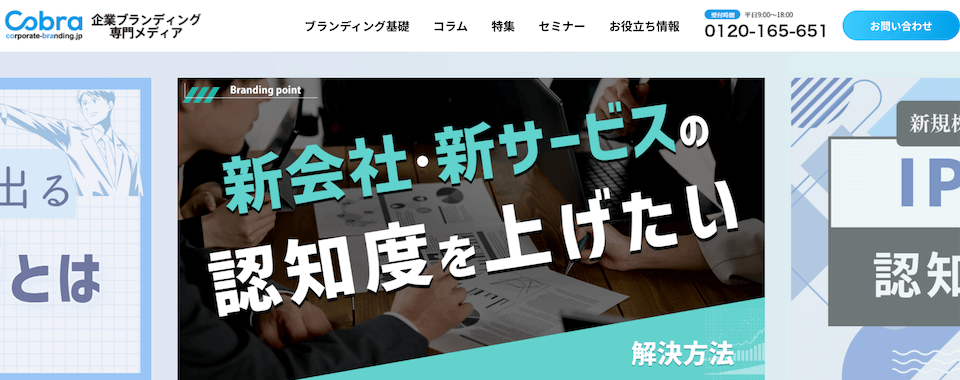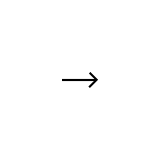47
プロが教える"外さない"ブランディングの依頼方法
外さない依頼と進め方で、成果は決まる。
ブランディングを依頼したいけれど「失敗したくない」「信頼できるパートナーを見つけたい」方は必読です。
プロが教える“外さない”ブランディングの依頼方法
ブランディングを依頼したいけれど「失敗したくない」「信頼できるパートナーを見つけたい」。そう考える方は多いのではないでしょうか。実はブランディングは、進め方や依頼の仕方次第で成果が大きく変わります。本記事では、プロの視点から見る「企業がブランディングに悩む典型的な課題」から「ブランディングを依頼する7つのメリット」をはじめ、「依頼前の準備」や「ブランディングの選定基準」、そして「企業ブランディング費用の目安」まで、成功のポイントを分かりやすく整理し、あなたの企業に最適なパートナー選びをサポートします。
そもそもブランディングとは?

ブランディングとは、ロゴ制作やプロモーション活動といった表面的な施策を指すものではありません。企業の理念や使命(MVV)を明確にし、CI(コーポレート・アイデンティティ)やVI(ビジュアル・アイデンティティ)を整備したうえで、Webサイトやパンフレットなどのブランドコミュニケーションを通じて、一貫した世界観を発信していく取り組みの総称です。その本質は「企業価値を最大化する仕組み」を構築し、顧客や求職者、さらには社会から選ばれ続ける存在へと企業を成長させることにあります。
ブランド構築は「見た目」だけではない
「ブランディング=デザイン」という誤解は根強いですが、本質はもっと深いところにあります。見た目の統一感だけではなく、企業がどんな存在意義を持ち、どのような価値を提供するのかを社会に伝える取り組みこそがブランド構築です。そのためには、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定や、企業文化を体現する言葉や表現が欠かせません。
一貫性が信頼と共感を生む
ブランディングでは「どの接点でも同じ世界観を体感できること」が重要です。CI・VIの設計を軸に、ロゴや色、デザインだけでなく、Webサイトや会社案内、採用ページ、広告、SNSに至るまで一貫性を保つことで、顧客や求職者は企業への信頼と共感を強めていきます。
企業価値を最大化する仕組み
ブランディングは短期的なキャンペーンではなく、企業の価値を長期的に高める仕組みづくりです。ブランドの存在意義やストーリーを浸透させることで、価格競争から脱し、優秀な人材を惹きつけ、顧客に選ばれ続ける強固な基盤を築くことができます。
企業がブランディングに悩む典型的な課題

多くの企業がブランディングに取り組むものの、その効果を十分に発揮できずに悩みを抱えています。競争が激しい市場で差別化できない、優秀な人材を採用できない、売上が伸び悩む。こうした課題の根底には「ブランドの伝え方」に不足があります。単なる商品やサービス訴求にとどまらず、企業理念や存在意義をいかに伝え、顧客や求職者の共感を得られるかが、今後の成長を左右します。
【課題1】差別化不足
競合がひしめく成熟市場では、自社の強みや独自性が十分に伝わらず、「結局どこも同じ」と見なされてしまうことが少なくありません。たとえ商品やサービスに優位性があっても、実際には顧客にとって小さな差にすぎないケースも多く、ブランディングが不十分だとその価値は埋もれてしまいます。その結果、価格以外で選ばれる理由を打ち出せず、消耗的な価格競争に巻き込まれ、シェア拡大が難航するという課題が生じています。
【課題2】採用難
人材不足が常態化するいま、優秀な人材に選ばれるためには「自社の魅力をどう伝えるか」が採用活動の成否を大きく左右します。給与や待遇といった条件面だけでは他社との差別化が難しく、求職者が共感するのはむしろ「理念」「文化」「働く環境」といった無形の価値です。こうしたブランド価値を効果的に発信できなければ、自社に興味を持ってもらう前に選択肢から外され、採用活動は非効率に終わってしまいます。
【課題3】売上停滞
ブランドの打ち出し方が曖昧なままでは、顧客の心に強い印象を残せず、リピートや紹介といった次の購買行動につながりにくくなります。その結果、新規顧客の獲得に依存せざるを得ず、コストだけが膨らみ、売上は頭打ちに。持続的に成長していくためには、ブランドの存在意義やストーリーを鮮明に伝え、顧客の共感と信頼を育むブランディング施策が不可欠となります。
ブランディングを依頼する7つのメリット

ブランディングは自社だけで進めようとすると、どうしても主観や部門ごとの利害に引きずられ、成果が限定的になりがちですが、外部のプロフェッショナルに依頼することで、客観的な視点や専門的なノウハウを取り入れながら、戦略設計からデザイン、発信までを一貫して推進する施策が可能となります。
その結果、社内合意のスムーズ化、採用と営業の両立、ブランド資産の体系化、効果検証や改善の仕組み化など、多くのメリットが得られます。ここでは、企業がブランディングを外部に委ねることで得られる「7つの価値」を具体的に解説します。
【メリット1】経営と現場の合意形成のファシリテーション
ブランドプロジェクトでは、経営層・事業部門・人事・広報など多様な部門の意見が交錯し、方向性がぶれやすいのが実情です。外部パートナーがファシリテーターとして入ることで、ワークショップや要件定義を通じて「誰に、どんな価値を届けるのか」を共通言語化。利害の異なる関係者の視点を整理し、初期段階で合意形成を図ることで、後工程の迷い・対立・手戻りを最小化します。
《施策例》
・部門横断ワークショップ(経営層・人事・営業・広報を集め、価値提供の定義を合意)
・ブランドパーパス策定セッション(ポストイットやを用いた議論)
・ブランドピラミッド(理念→価値→行動指針)を作成し、共通言語化
・合意形成後の「ブランド宣言」文書を社内配布
【メリット2】採用と顧客獲得を両立する“両利き”設計
多くの企業が「採用用」「営業用」と発信を分断しがちですが、ブランドは一つです。コーポレート、採用、営業支援(パンフレット・Web・動画)を同一トーンで統合し、外部(顧客)と内部(人材)の双方に通じる物語を描くことが可能です。これにより「この会社で働きたい」と感じる人材と「この会社に依頼したい」と思う顧客を同時に惹きつけ、応募者の質・商談の質をともに引き上げます。
《施策例》
・採用サイトとコーポレートサイトのデザイン・コピーに整合性を確保
・営業パンフレットと採用パンフレットを同じトーン&マナーで制作
・ブランドムービーを「採用説明会」と「営業プレゼン」の両方で活用
・SNS発信を「社員紹介×事業紹介」として兼用設計
【メリット3】ブランド資産の体系化(ガイドライン&アセット管理)
ロゴやカラー、タイポグラフィ、写真、コピーなど、ブランド表現に関わる要素を体系化し、ガイドラインやテンプレートに落とし込むことで「誰がつくってもブレのない世界観」が担保されます。さらに、グローバル拠点や複数代理店との協働でも表現がぶれることなく、一貫した世界観を維持。これにより、ブランド資産を積み重ねるほどに強固で再現性のある発信体制が整います。
《施策例》
・ランドガイドライン(ロゴ仕様、カラーコード、フォント、写真ルール)を制作
・名刺・封筒・スライドテンプレートなど共通データを配布
・デジタルアセット管理(DAM)ツールを導入し、拠点・代理店で共通利用
・ブランドらしい言葉づかい(定型表現 など)を整備し、統一感を確保
【メリット4】リサーチと計測による再現性の確保
従来の「感覚と経験」に頼った判断から脱却し、市場調査・競合分析・顧客インタビュー・ユーザーテストなどを基盤に意思決定を行うことができます。さらに、ブランド施策をKPIやアナリティクスで定量評価し、ローンチ後も改善サイクルを回すことで投資の妥当性(ROI)を可視化。単発で終わらない、再現性の高いブランド運営が可能になります。
《施策例》
・顧客アンケート調査(ブランド認知・好感度・購買理由の把握)
・競合ベンチマーク分析(Web、広告、採用コンテンツの比較)
・求職者向けインタビュー(応募動機や離脱理由の調査)
・Web解析・SNS分析によるブランド接点ごとの効果測定
・KPIダッシュボード(認知→応募/商談→成約の指標を可視化)
【メリット5】スピードと品質の両立(並行工程の設計)
ブランディングには「戦略を固めるまで制作に入れない」というジレンマがつきものです。外部の専門チームは、戦略・コンテンツ・デザイン・実装を並行して進めるプロジェクト設計により、意思決定の“待ち時間”を短縮。短納期であっても品質を落とさず、スピード感と完成度の両方を実現します。
《施策例》
・「ブランド戦略の叩き台」と「デザイン仮案」を並行して検討
・プロトタイプサイトを先行公開し、フィードバックを反映
・コンテンツ制作とガイドライン策定を同時進行
・アジャイル型進行(週次レビューで戦略・デザインを都度調整)
【メリット6】リスクマネジメント(法務・権利・表記)
ブランド資産は一度世に出れば、修正や回収が難しく、リスクは見過ごせません。著作権・肖像権・表記ルール・業界特有の法規制などをプロセス内で丁寧にチェックすることで、後から差し替えやトラブルに発展するリスクを最小化。安心して長期にわたって活用できる“法務的にも強いブランド資産”を積み上げます。
《施策例》
・著作権・肖像権チェックリストの導入
・モデルリリース(出演者の使用許諾)を必ず取得
・医薬・食品・金融など業界特有の広告規制に基づく表現確認
・法務部・外部弁護士とのレビュー体制を構築
・公開前チェックフローに「法務承認」を組み込み
【メリット7】内製化の支援(運用設計とトレーニング)
ブランドはローンチして終わりではなく、日々の運用で磨かれていきます。外部パートナーは、更新フローや役割分担を設計し、運用マニュアルやチェックリストを整備。さらにトーン&マナー講座や実務トレーニングを通じて担当者を育成し、外部依存ではなく自社で回せる仕組みを構築します。これにより継続コストを抑えつつ、発信のスピードと品質が高まります。
《施策例》
・ブランド発信マニュアル(SNS投稿例、トーン&マナー集)を作成
・定期勉強会(広報・人事・営業向けにコピーやデザインの研修)
・Web更新マニュアルや動画マニュアルを整備し、担当者を育成
・デザインテンプレート(PowerPoint/Illustrator/InDesign)を提供
・定期レビュー会で、内製コンテンツを外部が添削
依頼前に整理すべき3つの準備-成功の土台づくり
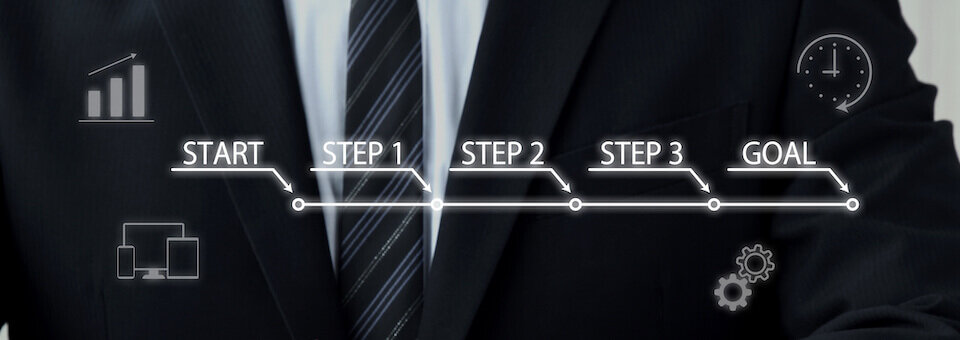
ブランディングを外部に依頼する際、成果を大きく左右するのは「依頼前の準備」です。ゴールが曖昧なままでは、提案の質も進行のスピードも落ち、期待した成果につながりません。だからこそ依頼に入る前に、目的の明確化・ターゲット像の共有・予算と期間の設計の3点を整理しておくことが大切です。これらを言語化し共有することで、提案内容はより的確になり、合意形成もスムーズになり、結果としてブランディング効果の最大化をもたらします。
【準備1】目的の明確化(売上UP/採用強化/周年事業/新規事業など)
ブランディングを依頼する際に最も重要なのは、「何を達成したいのか」の目的の明確化です。売上UP/採用強化/周年事業/新規事業など、目的が曖昧なままでは施策が散漫になり、効果検証も難しくなります。逆に、目的を数値化し具体的に言語化できれば、提案の質と進行速度は格段に高まり、社内外の関係者の共通認識もスムーズに形成されます。
《ねらいの例》
・(作る物=アウトプットではなく、変えたい状態)
・SMARTで具体化(いつまでに/誰に対して/どれだけ)
・KPIツリーで分解(最終指標→中間指標→行動指標)
《目的別の例》
・売上UP:6ヶ月で商談創出数+40%、平均単価+10%、サイトCVR2.0→3.0%
・採用強化:四半期のエントリー数+50件、内定承諾率+15pt、説明会満足度4.6/5以上
・周年事業:社内エンゲージメントスコア+10pt、メディア露出30件、コーポレート検索数+25%
・新規事業:申込300件、NPS(ネット・プロモーター・スコア)+30、有料転換率10%
《前提の例》
・Goal:誰に・何を・いつまでに・どの状態に
・Non-Goal(やらないこと):短期の指名採用は追わない、海外展開は次期 など
・制約条件:法規・表記、必須関与者、使える既存資産、禁止表現 など
【準備2】ターゲット像の明確化(顧客/求職者/投資家など)
ブランディングの成否を分けるのは、「誰に届けば成功なのか」をどれだけ具体的に描けるかです。ターゲット像が曖昧なままでは、表現がぶれ、社内での議論も堂々巡りになりがちです。一方、ペルソナを整理し「この層に確実に響けば成果につながる」というターゲット像を1枚にまとめておけば、判断軸が明確になり、施策全体の精度とスピードが格段に高まります。
《基本設計例》
・プライマリ/セカンダリを区別(最重要層に資源を集中する)
・DMU設計(意思決定者・影響者・実務ユーザーの三者を設計する)
・JTBD視点(顧客が本質的に求める価値を提供する視点を言語化する)
《ペルソナ設計例》
・基本属性(年齢・職種・役職・年収・地域)
・選定基準(必須:実績・納期/加点:デザイン品質・伴走力)
・意思決定プロセス(情報源→比較→稟議→決裁)
・メッセージマップ(主張/理由/証拠/誘導)
・現状の課題/阻害要因(比較材料がバラバラ、リスク説明不足)
《採用向けペルソナ例》
・26卒理系/研究室多忙/安定志向だが裁量を求む
・傾向:知的好奇心が強く、チャレンジできる環境を望む
・訴求ポイント:入社3年の成長モデル/配属後のOJT設計/先輩の失敗談
・魅力の根拠:研修カリキュラム、離職率、評価制度の透明度
・現状の課題:仕事内容が抽象的、成長環境の実像が不明
【準備3】予算・期間の目安(相場感と優先順位)
ブランディングを依頼する際に見落とされがちなのが、予算と期間の設計です。ここが曖昧なまま進めると、提案内容が現実とかけ離れたり、途中で追加費用やスケジュール遅延が発生して手戻りが増えてしまいます。逆に、初めに「どの範囲を、どの品質で、どの速度で実現するのか」という“器”を明確にしておけば、提案は具体性を増し、合意形成や進行もスムーズになります。さらに、要件の優先順位づけや別枠費目の切り分けを行うことで、無駄のない投資配分と実現性の高いプロジェクト進行が可能となります。
《策定事項例》
・範囲×品質×速度のトレードオフを明示(最優先事項の決定)
・MoSCoWで要件優先度付け
※Must(対応必須)、Should(対応すべき)、Could(できれば対応)、Won't(対応不要)
・フェーズ設計で見通し共有
(1)調査・戦略:3–6週(リサーチ/ポジショニング)
(2)クリエイティブ:12–24週(CI/VI、キークリエイティブ、コピー)
(3)実装:4–8週(Web、パンフ、動画の優先順位)
(4)ローンチ後:90日計測→改善サイクルを予定
・別枠費目として切り分け:撮影・イラスト制作・翻訳・広告費・ツール費(DAM/MA等)・法務レビュー
ブランディング会社4つの選定基準-パートナー選びで成果が決まる

ブランディングの成否を大きく左右するのは、「どの会社に依頼するか」というパートナー選びです。同じ予算や期間でも、選ぶ相手によって成果の質や持続性は大きく変わります。だからこそ、安さや表面的なデザイン力だけで判断するのではなく、実績・提案力・コミュニケーション力・料金体系の透明性という4つの視点から見極めることが大切です。
【選定基準1】 実績(同業界・同規模での成功事例)
自社に近い業界や規模での実績は、その会社がどれだけ自分たちの課題を理解し、成果につなげられるかの重要な判断材料です。単なるデザイン事例の数ではなく、「どんな課題にどう取り組み、どんな成果を出したのか」 を確認しましょう。
【選定基準2】 提案力(戦略からデザインまで一貫対応か、部分特化型か)
ブランディングは戦略・デザイン・発信が一体で機能してこそ成果が発揮されます。そのため、ブランディング施策を一貫して対応できる会社なのか、あるいは部分的な強みに特化しているのかを見極めることが大切です。自社の課題に応じて、総合力を求めるのか、特定領域に強いパートナーを選ぶのかを判断しましょう。
【選定基準3】 コミュニケーション力(伴走できるか/説明が分かりやすいか)
ブランディング・プロジェクトは年単位に渡る実施も珍しくないため、相互理解と信頼関係が欠かせません。専門用語ばかりでなく、わかりやすい言葉で説明してくれるか、社内の意見を整理し伴走してくれるかといったコミュニケーション力も、成果を左右する大きな要素です。
【選定基準4】 料金体系の透明性
費用構造が不透明だと、後からの追加請求や想定外のコストが発生し、トラブルの原因になります。どの範囲が基本料金に含まれ、撮影や翻訳、広告出稿といった別費用がどの程度かかるのかを明示してくれる会社を選びましょう。
【注意!】 ブランディングのよくある失敗例
ブランディング会社を選ぶ際、判断を誤ると時間もコストも無駄になり、成果につながらないリスクがあります。特に陥りやすいのが「安さだけで選ぶ」「戦略なしでデザインを発注する」といったケースです。
◉安さだけで選ぶ
初期費用が安く見えても、戦略不足や追加費用で結果的に割高になるケースがあります。
◉戦略なしでデザイン発注する
見た目は整っていても、企業の価値やターゲットに響かず、成果につながらないことが少なくありません。
これらの失敗例を避けるためにも、前述する実績・提案力・コミュニケーション力・料金透明性という4つの視点を基準に選定することが、後悔しない依頼につながります。
ブランディングのご依頼からブランド開発の流れ

ブランディングは、企業価値の言語化から具現化を経て、社会に伝えるまでの一連のプロセスです。デザインを納品して終わりではなく、ヒアリングから分析・戦略策定を経て、メッセージやロゴ、ガイドラインを整備し、Web・動画・パンフレットなどに展開していきます。さらには、空間やユニフォームといったリアルコミュニケーションでの接点に広げることで、社内外で一貫したブランド体験を生み出します。ここでは、そのステップを分かりやすくご紹介します。
【Step1】ご契約前|企業ブランディングの検討
1.お打ち合わせ・ヒアリング
ビデオ会議またはご面談にて、企業・事業・製品・サービス詳細や目標・課題などを伺い、ご希望要件を整理していきます。初回のお打ち合わせはご相談内容により最長2時間程度を要します。
2.プラン提案
ご希望要件に応じたプランをご提案。施策内容やご納品までの流れを詳細までご説明させて頂き、ご不明点を解消していきます。また、その後もお打ち合わせを重ね、ご納品までの暫定スケジュールを策定していきます。
3.ご契約
ご希望要件が確定次第、ご契約条件を整え、契約書類の取り交わしを行うとともに、キックオフ・ミーティングに向けたヒアリングシートの共有やスケジュール調整を行います。
【Step2】企業・製品の理解|企業ブランディングに向けたヒアリング
4.キックオフ・ミーティング(オリエンテーション)
ご契約締結後、クライアントを深く理解することを目的に、2時間程度のキックオフ・ミーティング(オリエンテーション)を実施します。表面的に見えている情報だけでなく、企業の思いや潜在的な魅力をヒアリング形式で掘り下げ抽出していきます。
5.キーマンインタビュー
基本方針として掲げる企業理念や経営理念、中核概念として掲げるMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、そして短期・中期経営計画や運営方針の確認を中心に行うキーマンインタビューは、ブランドの目指す方向性の明確化を目的としたインタビューとなります。経営者層の思いや目標を理解することで、より機能するブランドの開発を目指します。
【Step3】価値を見つける|企業ブランド分析
6.マーケティング環境分析(PEST/SWOT/3C/4P・4C/STP)
各種フレームワークを用いて環境分析を実施。企業を取り巻く内部・外部の経営環境を分析することで、本質的な課題の抽出から潜在的価値の発掘を行います。
7.マーケティング調査(ネットリサーチ/グループインタビュー/ホームユーステスト/他)
必要に応じてマーケティング調査を実施。消費者の定量データを収集するネットリサーチや、消費者の定性的な意見・情報を収集するグループインタビューを実施し、アイデアの種を発掘していきます。
【Step4】価値を定める|ブランドのバリュープロポジション策定
8.KSF(重要成功要因)策定
これまでの調査・分析結果から自社優位性を定義し、KSF(重要成功要因)を策定。自社の強みを明確化することで、ブランディング・プロジェクトチームへのブランド共有が可能となるため、より明確に共通認識を持つことができます。
9.フォーカスポイント決定
前項で定義された自社優位性とKSF(重要成功要因)を検証し、ブランドがフォーカスするポイントを決定。ブランドの言語化・具現化へと進めていきます。
【Step5】対象を定める|ブランド・ポジショニングの策定
10.ターゲティング
市場を細分化(マーケット・セグメンテーション)し、自社優位性が最も機能する市場を選定(ターゲティング)。具体的な顧客層を選定することにより、マーケティング戦略の効果を最大化していきます。
また、ターゲットとする市場で自社優位性を最大限に発揮できるポジショニングを見直し、提供価値の最大化を図ることでブランドの再活性化を図ります。
【Step6】価値を磨く|ブランドの明文化・具現化
11.ブランドメッセージ開発
企業の中核概念となるミッション・ビジョン・バリューをはじめ、ブランドコンセプトやブランドストーリー、タグラインなど、MI(マインド・アイデンティティ)を定義することでブランドの言語化を図ります。
《代表的なブランドメッセージ》
パーパス/MVV/ブランドコンセプト/タグライン/ブランドヒストリー/ など
12.VI(ビジュアル・アイデンティティ)開発
ブランド価値やコンセプトを可視化したブランドシンボルやロゴデザインなどを中心に、ブランドカラーや指定書体などのデザイン要素一式を定義していきます。定義された規定はVIマニュアル、VIレギュレーションまたはブランドガイドラインとしてまとめ、以降ブランド運用の基軸となっていきます。
《開発するVI》
LOGO /ロゴレギュレーション/ブランドガイドライン など
【Step7】価値を伝える|ブランドコミュニケーション開発
13.Webサイト制作
情報のプラットフォームとなるWebサイトは、VIの中でも最も重要なブランドコミュニケーションを担います。策定されたVIに準拠し、ブランドデザインの統一を図ることで、ブレることなくブランドの世界観を伝えていくことが大切です。
《代表的なWebサイト》
Webサイト(コーポレート/ブランド/採用/LP/他)/ECサイト(Welcart /ECCUBE/ASP/他)/オウンドメディア(情報発信サイト/ウェブマガジン)など
14.動画制作
Webサイトや紙媒体など、写真や文字情報だけでは伝えきれない情緒を瞬時に伝えることができるのが、動画最大の特徴だと言えます。また、視聴者が受動的に情報を得ることができるため、短時間で膨大な情報コミュニケーションを図ることができます。
近年ではYouTubeの爆発的な普及や通信速度の急速な発展により、有線・無線環境を問わず、どこでも動画視聴が可能なため、WebサイトやSNSに動画コンテンツを多数設けるなど、動画でのブランドコミュニケーションもブランディングに不可欠な要素のひとつとなっています。
《代表的な動画》
ブランド動画/採用案内動画/プロモーション動画(TVCM/WebCM/SNS)/アニメーション動画 など
15.パンフレット制作
ターゲットに能動的なアピールが可能なパンフレットは、ブランドの世界観と情報をバランスよくアピールできるコミュニケーションツールのひとつです。情報を一方的に伝えるのではなく、魅せるデザインで「もっと深く知りたい心理」を刺激することが大切です。Webでは伝えきれないプレゼンテーションが可能な点も、パンフレットならではの魅力です。
《代表的なパンフレット》
会社案内パンフレット/採用案内パンフレット/営業パンフレット/製品パンフレット/商品カタログ/総合カタログ/リーフレット など
16.空間デザイン
建物・室内の設計・デザインをはじめ、空間を演出するインテリアコーディネートや商品ディスプレイ、家具や植栽に至るまで、空間デザインのアートディレクションを行い、ブランドの世界観を具現化していきます。
17.ユニフォーム制作
作業服や事務服など、ブランドイメージを表現するユニフォームは、ただの作業着・仕事着ではなく、社会的な立場を示す制服です。オリジナルデザインのユニフォームは社員のモチベーション向上に寄与し、職場の一体感を強めます。
企業ブランディング費用の目安

企業ブランディングは「戦略設計」から「ビジュアル開発」「Webやパンフレット制作」「動画発信」に至るまで、多岐にわたる要素で構成されます。費用は目的や規模によって大きく変動しますが、相場感を把握しておくことで、無理のない予算計画と優先順位づけが可能になります。ここでは、ブランド戦略設計や理念開発(パーパス・MVV・クレド)、VI開発、Web・パンフレット・動画制作まで、それぞれの費用目安を整理します。
企業ブランディング費用の目安一覧
《ブランド戦略設計》
◉クリエイティブ・ディレクション:企業ブランディング実施に伴う進行管理費
費用(税別):30万円〜
《MI開発》
◉パーパス開発:存在意義や企業が社会に対して果たすべき役割の言語化
費用(税別):30万円〜
◉MVV開発:ミッション・ビジョン・バリューの言語化
費用(税別):90万円〜
◉クレド開発:行動指針の言語化
費用(税別):50万円〜
◉ブランドコンセプト・タグライン開発:ブランドの本質を表すメッセージの言語化
費用(税別):60万円〜
◉ネーミング開発:会社名・サービス名の提案や選定
費用(税別):50万円〜
◉クレドブック制作:理念浸透に向けた社員向けハンドブックの制作
費用(税別):100万円〜
《VI開発》
◉ロゴ開発:ロゴマーク・ロゴタイポグラフィなどのデザイン
費用(税別):50万円〜
◉ブランドガイドライン制作:ブランドルールの文書化
費用(税別):30万円〜
◉ロゴ基本レギュレーション制作:ロゴ運用マニュアルの文書化
費用(税別):10万円〜
《Web制作》
◉コーポレートサイト制作:企業ホームページの制作
費用(税別):300万円〜
◉採用サイト制作:求職者向けWebサイトの制作
費用(税別):200万円〜
《パンフレット制作》
◉会社案内制作:企業の信頼獲得に向けたパンフレットの制作
費用(税別):100万円〜
◉採用案内制作:求職者アプローチ用パンフレットの制作
費用(税別):100万円〜
《動画制作》
◉ブランド動画制作:企業ブランディングに向けた動画の制作
費用(税別):200万円〜
◉採用動画制作:採用強化に向けた求職者向け動画の制作
費用(税別):150万円〜
成功事例で見るブランディング7選

具体は、最良の教科書です。本章では、業界・規模の異なる7社の実例を取り上げ、課題→戦略→クリエイティブ→成果までを一気通貫で紹介。「なぜその意思決定をしたのか」「何が効果を生んだのか」を明らかにし、明日からの実務に転用できる学びを抽出します。
プロジェクトは、代表をはじめとするコアメンバーとのディスカッションからスタートしました。既存理念である「最適解を追求する」を基盤に、未来へ向けて大切にすべき価値を言語化。そこからタグライン・ブランドコンセプトを策定し、MIとロゴを構築しました。アウトプットはアウターブランディングとインナーブランディングの両面に展開され、社員が誇りを持って目指す姿を示すクリエイティブとして浸透しています。
創業100周年を契機に始まったリブランディングプロジェクト。ミッション・ビジョン・バリューの策定からブランドコンセプト・タグライン開発、そして新社名のネーミングまでを一貫して実施しました。ロゴを中心に、コーポレートサイト・ブランド動画・会社案内パンフレット・営業ツール・ピンバッチに至るまでトータルでVIを刷新。経営企画部と社員の積極的な参加により、未来を見据えた新しい企業像を形にしました。
新たなValues「力強い警備」と「美しい警備」を掲げ、ロゴの刷新をはじめ、会社案内、コーポレートサイト、ブランドムービー、名刺や封筒など幅広いツールを統一。Purpose「その道を通る、その場所を訪れるすべての人の、今日と未来を守る。」を中心に据え、警備業としての誇りと使命を力強く発信しました。さらに、社員総会のオープニング動画やメイキング映像を制作し、インナーブランディングを強化。社内の一体感と外部への信頼醸成を同時に実現しました。
ブランディング事例vol.4|日進医療器株式会社[NAUTUS]
新たに開発した「アクティブ車いす」5機種の製品ブランディングを担当。ネーミングやロゴ、Webサイト、コンセプトカタログを一貫して制作しました。徹底したヒアリングから導き出されたのは、機能性とスタイリッシュなデザインで他社との差別化を狙う強いこだわり。その意志を体現するため「ほっこり禁止・とがった表現で」という制作ルールを設定し、挑戦的かつ魅力的なブランド表現を実現しました。ローンチ後は展示会でも高い評価を獲得し、同社の新しい一歩を後押ししました。
事業開始から順調に園児・保育士を集めてきたゆめいろ・なないろ保育園。将来を見据え「選ばれる保育園」になるためのブランディングが求められました。各園の園長先生とのワークショップから理念・方針・目標を整理し、コンセプトを設計。その上でロゴ・Webサイト・ステーショナリーなどを開発しました。保護者に信頼され、子どもたちと保育士が誇りを持てるブランドを築くための基盤を整えました。
まとめ:ブランディングは依頼の仕方で結果が変わる
ブランディングは、理念の言語化からデザイン・発信まで一貫して企業価値を最大化する、企業活動にとって必要不可欠な取り組みのひとつです。依頼時には「目的・ターゲット・予算」を事前に整理・準備し、実績や提案力など4つの基準でパートナーを選ぶことが大切です。正しい進め方と適切な投資により、差別化・採用力・売上向上を同時に実現していきましょう。
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治