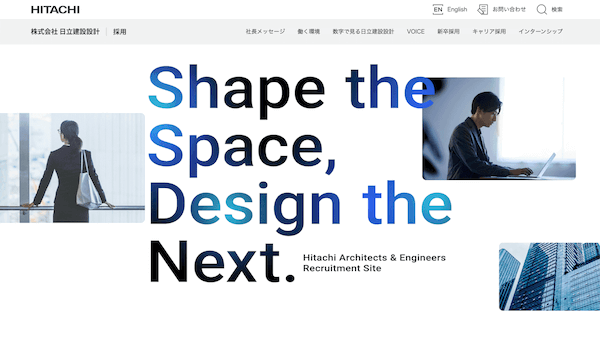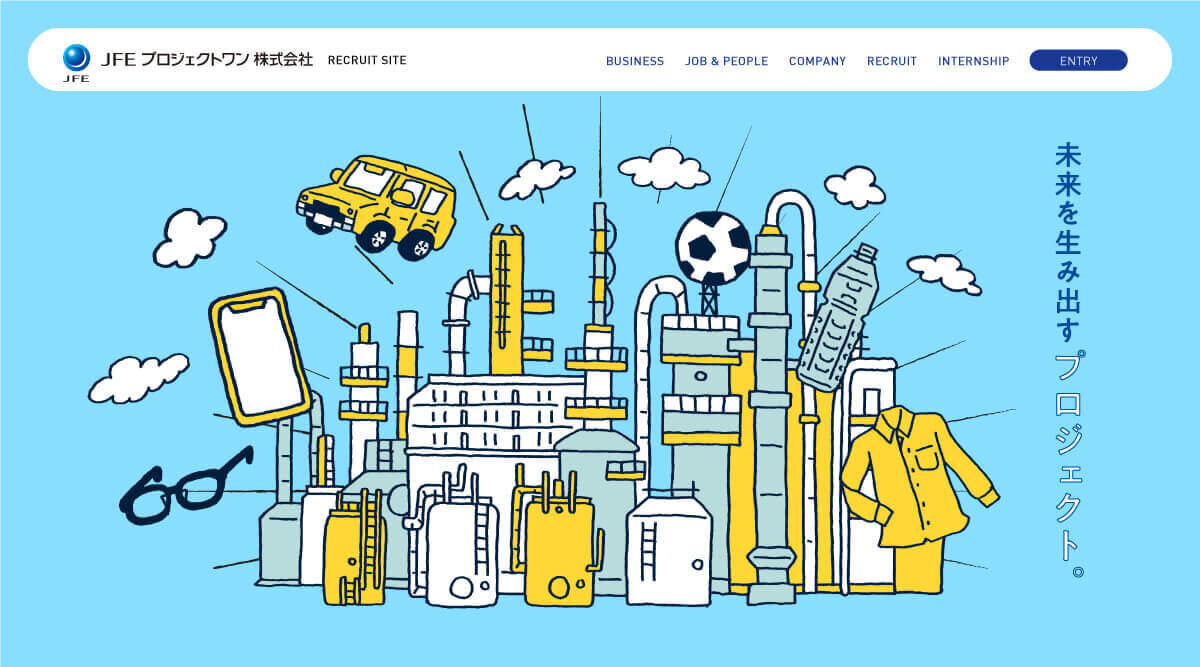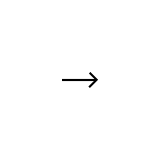99
採用サイト制作の費用相場と、制作費削減のポイント
採用サイトの費用を、すべて明らかに。
目的・ターゲット・要件を決めれば、見積もりはブレない。相場から削減ポイントまで一気に解説します。
採用強化に不可欠な採用サイトの制作費、一体いくらかかるのか?
採用市場が激化する中、採用サイトは「会社の顔」として応募者との最初の接点を担います。また、理念や事業内容、社員の声を魅力的に発信できるかどうかは、応募数や内定承諾率にも大きく影響します。では、そんな重要な採用サイトの制作には一体どのくらいの費用がかかるのでしょうか? 実はその相場はサイトの規模や目的によって大きく変わります。本記事では、その内訳やポイントを丁寧に解説していきます。

【補足1】採用サイトとコーポレートサイトとの違い
コーポレートサイトは顧客や投資家、取引先といった幅広いステークホルダーに向け、会社概要や事業内容、実績などを発信する企業の顔となるWebサイトです。一方、採用サイトは、「求職者」という明確なターゲットに特化し、仕事内容や社風、社員の声など応募者が知りたい情報を中心に構成されます。つまり、同じ企業の情報発信でも目的と伝えるべき内容が異なるため、採用活動を強化するには採用サイトの存在が不可欠となります。
【補足2】Webサイトが応募者に与える第一印象
応募者がエントリーを検討する際、企業情報詳細を収集する先は、コーポレートサイトや採用サイトになることが一般的です。故に、Webサイトのデザインや情報の充実度は、応募者に「信頼できる会社か」「自分に合う環境か」といった印象を与える重要な要素となります。写真や動画、わかりやすい導線設計により、応募者は自分の将来を具体的にイメージできるようになります。第一印象を左右するコーポレートサイトや採用サイトは、まさに「会社の窓口」といえるでしょう。
【補足3】採用サイト制作が必要となるタイミング
採用サイト制作を検討すべきタイミングは、単に「人を採用したいとき」だけではありません。たとえば、新卒採用を本格的に始めるとき、離職率の高さに課題を感じているとき、企業の成長や周年を機にブランディングを刷新したいときなどが挙げられます。こうした局面では、従来の求人媒体やコーポレートサイトだけでは十分に魅力を伝えきれず、採用サイトの役割が一層大きくなると言えます。
何を明確にしたら、採用サイトの制作費が正しく算出できるのか?

制作費用を正しく算出するには、まず「採用サイトの目的」と「ターゲット像」を明確にすることが不可欠です。新卒採用なのか中途採用なのか、母集団形成を重視するのかブランディング強化が狙いなのかによって、必要なコンテンツや機能は大きく変わります。さらに、掲載したい情報の量(ページ数)、写真や動画の有無、採用管理システムとの連携など、要件を整理することで、見積もりはぐっと正確になります。
◉採用サイト制作の目的とは
採用サイトをつくる目的は単なる「求人情報の掲載」ではありません。コーポレートサイトや求人媒体では伝えきれない、「自社ならではの魅力」や「働くリアルな姿」 を応募者に届けることにあります。具体的には、次のような目的が挙げられます。
・母集団形成:求人媒体任せにせず、自社サイトを通じて直接応募を増やす
・企業理解の促進:理念・事業内容・社員の声を発信し、理解度を高める
・ミスマッチ防止:働き方や社風を事前に伝え、入社後のギャップを減らす
・ブランディング強化:採用だけでなく、会社の信頼感やブランド力を高める
つまり採用サイトは、応募者にとっては「入社前に会社を体験する場」、企業にとっては「最適な人材と出会うための入口」としての役割を担っているのです。
◉ターゲット像とは
効果的な採用サイト制作は、「誰に向けて情報を発信するのか」 を明確にすることが大切です。これがターゲット像です。たとえば…
・新卒採用:学生が気になるのは「働く人の雰囲気」や「成長できる環境」
・中途採用:キャリアやスキルを活かせる職場かどうかが重要
・専門職採用:仕事内容の具体性やスキルアップ支援の有無が評価ポイント
ターゲット像を定めることで、採用サイトに盛り込むべき要素が明確になります。例えば、社員インタビューや1日の仕事の流れ、キャリアパス紹介といったコンテンツが必要かどうかが判断しやすくなります。また、ターゲットに響く言葉の選び方や、どのようなビジュアル表現が効果的かも見えてきます。さらに、求人媒体やSNSなど、どの媒体と連携し、どのような導線を設計すべきかが明確になるため、結果として応募者の心に刺さるサイト設計が可能になります。
制作費を抑えつつ、魅力的なサイト採用サイト制作を行うには?

限られた予算でも工夫次第で効果的な採用サイトは実現できます。たとえば、自社で準備できる写真や原稿を活用すれば外注コストを削減できますし、テンプレートデザインをベースに部分的なカスタマイズを加える方法もあります。また、初期段階では必要最低限のコンテンツを公開し、応募状況やニーズに合わせて段階的に情報を追加するのも有効です。「費用を抑える=質を落とす」ではなく、「投資のメリハリをつける」発想が重要です。
【費用を抑えるポイント1】自社で準備できる写真や原稿を活用する
写真撮影や原稿制作をすべて外注すると、費用は大きく膨らみます。もし自社で用意できる部分があれば、できるだけ社内で準備することも大切です。たとえば、社内イベントや日常風景の写真を社内スタッフが撮影したり、社員紹介文を人事担当者が原案として書いたりすることで、外注費を抑えながらリアルで親しみやすいコンテンツを発信できます。
【費用を抑えるポイント2】初期段階では必要最低限のコンテンツを公開する
すべてのコンテンツを一度に制作しようとすると、時間も費用もかかります。まずは「仕事内容」「募集要項」「エントリーフォーム」など、採用活動に直結する最低限の情報から公開し、その後の運用フェーズでインタビュー記事や動画を追加していく方法もあります。段階的な追加公開により、初期費用を抑えつつ、採用ニーズの変化に柔軟に対応できます。
【費用を抑えるポイント3】採用サイトをLP型で制作する
多くのページを持つツリー構造の採用サイトではなく、1ページ完結型のランディングページ(LP)形式で制作すれば、構築コストを大幅に削減できます。LP型であっても、会社の魅力や募集要項、エントリーフォームをまとめることは可能ですので、まずはコンパクトに立ち上げ、効果を見ながら必要に応じてページを増やすアプローチは、スタートアップ企業や採用初期フェーズに特に有効です。
採用サイト制作をプロの制作会社に依頼するメリットと注意点
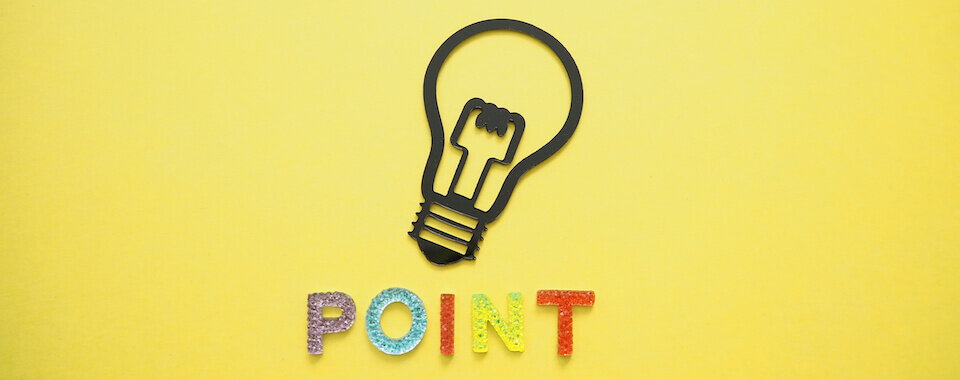
プロの制作会社に依頼する最大のメリットは、「応募者目線の設計」と「採用ノウハウに基づくコンテンツ提案」です。単なるデザイン会社ではなく、採用戦略や企画に強みを持つ制作会社であれば、求職者が何を知りたいかを踏まえた構成を提案してくれます。ただし、費用や実績だけで判断せず、自社の採用課題を理解し、運用まで伴走してくれるパートナーかどうかを見極めることが重要です。
【メリット1】最新の採用トレンドを反映できる
プロの制作会社は、業界ごとの事例や最新の採用動向を把握しています。そのため、自社だけでは気づけない求職者ニーズや時代に合ったデザイン・コンテンツを取り入れることができます。
【メリット2】採用広報を一貫してサポートしてくれる
採用サイト単体ではなく、採用動画、パンフレット、SNSなど複数チャネルを横断的に設計できるのも制作会社の強みです。統一感のある採用ブランディングを実現しやすくなります。
【注意点1】依頼時に注意すべきポイント
制作実績の数や費用だけで判断すると失敗につながることがあります。打ち合わせ時に「採用課題をどこまで理解してくれるか」「公開後の運用体制まで支援してくれるか」を確認することも大切です。
【注意点2】コストと成果のバランスを見極める
高額な見積もり=必ずしも効果的なサイトとは限りません。逆に安さだけを重視すると、採用ノウハウが不足し、応募につながらないサイトになることもあります。複数社を比較検討し、費用対効果を見極める視点が欠かせません。
では、採用サイト制作の費用相場は?

一般的に、採用サイト制作の費用相場は100〜500万円程度とかなりの幅があります。小規模な採用サイトであれば100〜150万円前後、中規模でオリジナルデザインやインタビュー記事を含める場合は150〜300万円程度、大規模でブランディングを全面的に打ち出す特設サイトとなると400万円以上になることも珍しくありません。自社の採用課題や目的に応じて、どの規模が最適かを見極めることが大切です。
◉小規模な採用サイト:100万円前後
シンプルな構成で、仕事紹介や募集要項、エントリーフォームなど、採用活動に必要な最低限の情報をまとめたサイトです。ページ数が少なく、最小限のアニメーション実装とすることが多いため、比較的低コストで立ち上げられます。新卒採用を小規模に始めたい企業や、求人媒体の補完として情報を整備したい企業に適しています。
◉中規模な採用サイト:100〜300万円程度
社員インタビューや1日の仕事の流れ、キャリアパス紹介など、求職者が知りたい情報を幅広く盛り込んだ構成です。オリジナルデザインやキーメッセージを取り入れ、写真撮影や取材記事を交えることで、企業の魅力をより具体的に伝えることができます。中途採用や新卒採用を本格的に強化したい企業にとって、費用と効果のバランスが良いモデルです。
◉大規模な採用サイト:400万円以上
採用ブランディングを全面的に打ち出し、動画コンテンツや特設ページ、応募管理システムとの連携など、多機能かつリッチな構成を実現するサイトです。ページ数も多く、コンテンツ制作やシステム開発に十分な投資を行うことで、採用広報の中心的な役割を果たします。大規模な新卒採用や複数職種の同時募集、企業ブランドの確立を狙う場合に最適です。
さらに、採用サイト制作費の内訳は?
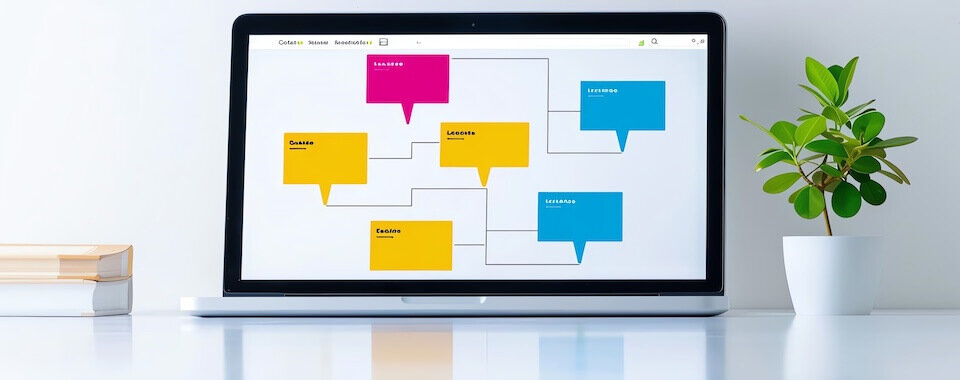
採用サイトの制作費は一見すると「まとめて○○万円」と示されることが多いですが、実際にはいくつもの要素が積み重なって構成されています。費用の内訳を理解することで、どこにコストをかけるべきか、逆にどこを工夫して抑えることができるかが見えてきます。ここでは、企画から設計、デザイン、コンテンツ制作、システム開発、そして公開後の運用まで、それぞれの工程にかかる代表的な費用項目を整理しました。
【制作費の内訳1】企画・設計費
・採用ターゲットや採用課題を踏まえた戦略設計
・サイト構成(ページ構成・導線設計・ワイヤーフレーム)
・コンテンツ企画(社員インタビュー、事業紹介、プロジェクト紹介など)
企画・設計は、全体の方向性を決めるための重要な初期工程となります。
【制作費の内訳2】デザイン制作費
・トップページ・下層ページのデザイン制作
・UI/UX設計(応募者が使いやすい導線づくり)
・スマホ対応(レスポンシブデザイン)
デザインクオリティは応募の母集団形成に大きな影響を及ぼします。
【制作費の内訳3】コンテンツ制作費
・原稿作成(コピーライティング・取材記事・社員インタビュー)
・写真撮影(オフィス、社員、イベントなど)
・動画制作(事業紹介動画、社員インタビュー動画 など)
企業の印象を左右し、応募者の心を動かす最大の要因となります。
【制作費の内訳4】コーディング・開発実装費
・デザインデータをWebサイトに実装
・レスポンシブ対応・ブラウザ検証
・SEO内部対策(メタ情報、構造化データ、表示速度の最適化 など)
デザインの再現とアニメーションや動画などを実装する工程です。
【制作費の内訳5】システム・機能開発費
・エントリーフォームや応募管理システムとの連携
・CMS(WordPress、Movable Type など)の導入
・検索機能、マイページ機能などの追加開発
機能が増えるほど利便性が上昇する一方、費用も上昇するポイントです。
【制作費の内訳6】テスト・公開・保守費
・公開前の動作テスト、セキュリティチェック
・サーバー・ドメイン設定
・公開後の更新代行、セキュリティ保守、運用サポート
公開後も安全な運用を行い、鮮度を維持するためのコストです。
採用サイト制作費を決定する主な要素は?
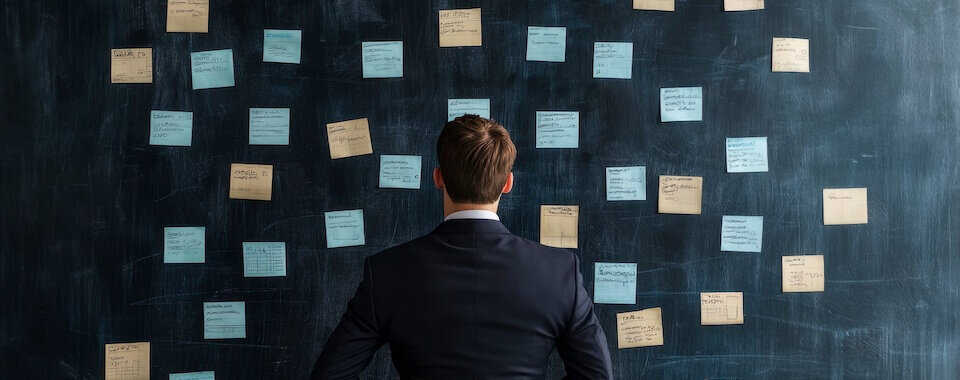
採用サイトの制作費は「一律いくら」と決まるものではなく、サイトの構成や機能、コンテンツの内容によって大きく変動します。シンプルなページ構成で最低限の情報を掲載するだけなら比較的安価に収まりますが、社員インタビューや動画コンテンツを取り入れ、応募者が働く姿をリアルにイメージできるサイトを目指すと、その分コストも上がります。どの要素に重点を置くかを整理することが、適切な予算設定の第一歩となります。
【要素1】ページ数と情報量
採用サイトに掲載するページ数や情報量は、費用を大きく左右する要因です。トップページと募集要項のみのシンプルな構成であれば費用は抑えられますが、社員インタビュー、仕事内容の紹介、1日の流れ、キャリアパス、動画コンテンツなどを盛り込むと、その分制作ボリュームが増え、コストも高くなります。応募者にどこまで情報を届けたいかによって、必要なページ構成を見極めることが重要です。
【要素2】機能追加
応募フォームや検索機能、採用管理システム(ATS)との連携、CMS(WordPressやMovable Typeなど)の導入といった機能面の追加は、利便性を高める一方、費用に直結します。ただし、過剰な機能追加は無駄なコストにつながる可能性があるため、自社の採用フローに合った必要十分な機能を選定することが大切です。
【要素3】写真・動画撮影
採用サイトに掲載する写真や動画のクオリティは、応募者の印象を大きく左右します。社内で撮影した簡易的な素材を活用すればコストは抑えられますが、プロのカメラマンや映像クリエイターによる撮影は、会社の雰囲気や働く人の魅力をより効果的に伝えることができます。特に社員インタビュー動画やオフィスツアー映像は、応募者が「働く姿」を具体的にイメージするための強力なコンテンツとなります。
【要素4】取材・原稿作成
サイトに掲載する文章を自社で用意するか、ライターや編集者に依頼するかにより費用は変動します。自社作成はコスト削減につながりますが、表現力や読みやすさに課題が残る場合があります。プロのライターに依頼することで、応募者に伝わりやすいコピーライティングや、読み進めやすい取材記事を制作でき、採用サイト全体のクオリティを高めることができます。情報を正しく、かつ魅力的に発信するためには重要な工程です。
公開後の運用を視野に入れた採用サイトに仕上げるポイントは?

採用サイトは「作って終わり」ではなく、公開後の運用が勝負です。例えば、情報の鮮度を保つため、募集要項や社員インタビューを簡単に更新できる仕組み(CMS)を整えることが肝要となります。また、アクセス解析や応募データをもとに改善を重ねることで、より効果的なサイトへと改善することもできます。採用広報のSNSや動画と連動させて情報発信の幅を広げることも、運用視点での重要なポイントです。
【運用ポイント1】更新のしやすさを設計段階から考える
公開後に情報を更新しにくく、最新情報を反映しずらいサイトは、すぐに「古い印象」を与えてしまいます。社内担当者が手軽に修正・追加できるCMSを導入することで、鮮度の高い情報を維持できます。
【運用ポイント2】データを活用した改善サイクル
Googleアナリティクスや応募フォームのデータを分析すれば、「どのページから応募が多いか」「どこで離脱が多いか」が明確になります。数字を根拠にした改善は、応募率の向上に直結します。
【運用ポイント3】他チャネルとの連動で拡散力を高める
採用サイト単体ではリーチに限界があります。InstagramやTikTokなどのSNS、採用動画、求人媒体とリンクさせることで、認知拡大と応募促進の相乗効果が期待できます。
【運用ポイント4】長期的なブランディング資産に育てる
継続的に情報を更新する採用サイトは、単なる「求人ページ」ではなく、会社の文化や価値観を伝えるブランディング資産になります。将来の応募者や取引先に対しても、信頼を築く効果を発揮します。
採用サイトの制作事例10選

優秀な人材を惹きつける採用活動において、採用サイトは「企業の顔」となる重要なツールです。近年は単なる求人情報の掲載にとどまらず、社員のリアルな声や企業のカルチャーを伝えるコンテンツ、親しみやすいデザイン、動画やイラストを駆使したストーリー性のある表現が求められています。ここでは、各企業が抱える課題をクリエイティブに解決した「採用サイト制作事例10選」をご紹介します。
◉株式会社国際電気|採用サイト(LP)制作事例
社会インフラ分野に強みを持つ国際電気は、学生に伝わりづらい専門性をビジュアルとコンテンツで解決。採用サイトではオリジナルイラストや社員の声を通して直感的に魅力を伝え、応募意欲を高めています。
◉株式会社日立建設設計|採用サイト(LP)制作事例
建設設計の魅力を伝えるため、採用サイトをマイクロサイトとして刷新。「Shape the Space, Design the Next.」のメッセージのもと、社員の声やプロジェクト紹介で仕事の理解を深めています。
◉アマヤ・パートナーズ税理士法人|採用サイト制作事例
採用サイトで「PARTNER FOR GROWTH」のメッセージを発信。Key動画や社員の声、制度紹介を通じて、成長を支援する職場環境とリアルな雰囲気を視覚的・具体的に伝えています。
◉株式会社不二製作所|採用サイト制作事例
オンリーワンのブラスト技術を持つ不二製作所。採用サイトでは「唯一無二」をキーワードに設計職の魅力を深掘り。社員インタビューや動画を活用し、独自性と社風を訴求しています。
◉協和ファーマケミカル株式会社|採用サイト制作事例
コーポレートサイトとは異なる明るく活発なデザインで、親しみやすさを演出。プロジェクト対談「ケミストーリー」などを通じて、難解な印象を払拭し、企業理解を深めています。
◉ JFEプロジェクトワン株式会社|採用サイト制作事例
親しみやすいイラストやアニメーションを用い、従来のプラント業界のイメージを一新。女性や若手にも伝わる「ワクワク」「ドキドキ」する採用サイトを構築しました。
◉ IT FORCE株式会社|採用サイト制作事例
「その技術に、志はありますか。」のメッセージで成長意欲をアピール。明るく柔らかいデザインで、自ら考え行動する人材への共感を生む採用サイトを展開しています。
◉ 株式会社ジョンマスターオーガニックグループ|採用サイト制作事例
「美しさを育てる人になる」をテーマに、自然なスタッフの表情やインフォグラフィックを活用。ブランドイメージを反映した採用サイトで応募意欲を高めています。
採用サイト制作でよくある質問
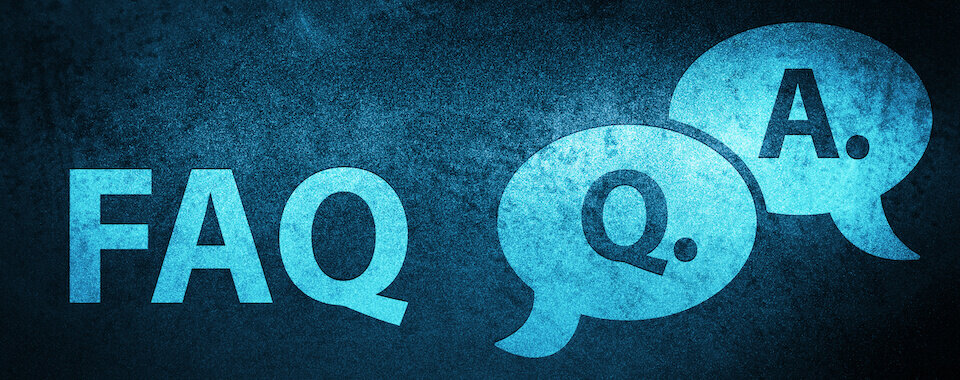
採用サイトの制作を検討する際、多くの企業が抱える疑問や不安は共通しています。
「サイトだけで応募は集まるのか」「スマホ対応は必要か」「どの程度を自社で準備すればよいのか」など、制作前に知っておくべきポイントは少なくありません。ここでは、採用サイト制作でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。検討段階での参考にしていただくことで、スムーズな制作進行と効果的なサイト運用につながります。
Q1.採用サイトだけで応募は集まりますか?
単体で効果を発揮することもありますが、採用サイトだけでは限界があります。そのため、求人媒体への出稿をはじめ、採用パンフレットの活用や採用動画の公開、InstagramやTikTokなどSNSとの連動で、母集団形成を図ることを推奨しています。
Q2.採用サイトのスマホ対応は必須ですか?
年齢を問わず多くの場合、求職者が求人情報を獲得し、情報収集するデバイスはスマホです。一方、多くの企業にエントリーする新卒大学生やキャリア層は利便性の高いパソコンを使いこなし、効率的に多くの情報収集を図るため、より多くの層にストレスのない情報提供を図るのであればスマホ対応は必須だと言えます。
Q3.採用サイトの企画やデザインは提案いただけるのでしょうか?
はい。もちろんご提案させて頂きます。目的やターゲットに最適化した企画の立案からTOPページを始め、各ページのデザイン制作、取材・原稿作成、写真・動画撮影、そしてコーディング実装に
Q4.文章やインタビュー記事は自社で用意する必要がありますか?
貴社でご用意いただいた情報を反映することも可能ですし、取材・文章作成からご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただく際は、プロのコピーライターが取材・文章作成を行いますので、ワンランク上の原稿制作が可能です。
Q5:写真や動画を自分たちで撮影しても問題ありませんか?
はい。問題ございません。写真や動画の明度や彩度はある程度の補正が可能ですので、ご相談ください。一方、ピントのズレやボケは補正不可となりますのでご注意ください。また、画像のレタッチや合成にも限界がございますため、出来るだけ撮影データをそのまま利用できるクオリティでご準備頂くことが重要です。
Q6:写真や動画撮影は必須でしょうか?
必須ではございませんが、写真や動画は採用サイトのクオリティに直結するため、求職者に響き届く採用サイト制作をご希望の際は、撮影からご依頼頂くことを推奨しています。採用サイト制作のプロフェッショナルならではのクオリティをご提供します。
Q7:採用サイト制作にはどのくらいの期間が必要ですか?
サイトの制作要件(ページ数やコンテンツ量、実装する機能など)や情報準備のご状況により制作期間は異なりますが、最短3ヶ月程度〜平均6ヶ月程度が制作期間の目安となります。公開希望日(納期)などがございましたら、予めご相談ください。
Q8:公開後の更新作業は自社でできますか?
採用サイト開発時にCMS(Contents Management System)を導入することで、管理画面より簡単に更新作業を行うことができます。但し、CMSの導入は、イニシャルコストを要するため、「更新の頻繁なページをCMS化」し、年1度の修正程度を要するページは修正のご依頼を頂くことを推奨しています。
Q9:更新や運用のサポート対応はお願いできますか?
はい。もちろん対応可能です。弊社では、年間での「運用管理契約プラン」と「スポット対応プラン」の2パターンがございますので、サイトの更新頻度やお客様側の社内リソースのご状況を伺い、最適なプランをご提案させて頂きます。
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治