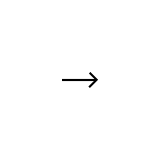128
グローバル化に向けた海外進出と戦略マネジメント
権限委譲することで、想定以上をモノにする。
ローカル市場のニーズを組み上げる現地拠点の自立化と、グローバル統合の効率性を両立して市場優位性を確立する。
企業の海外進出にある3つの手法
日本は近年、急激なグローバル化を遂げています。その背景には少子高齢化や人口減少による国内市場の縮小があり、日本企業の海外進出は、企業が成長するための必然であると言えます。一方、世界全体で見ると人口は現在も増加傾向にあり、市場規模が拡大し続けていることから多大な可能性を秘めていると言えます。海外のマーケットを視野に入れることで、日本国内市場の数倍・数十倍のビジネスチャンスを手にすることが可能となるのです。
では、どのような方法で海外進出を図るべきなのでしょうか。企業は海外進出にあたり、当初はいかにして自社製品を輸出するかが重要になりますが、グローバル化が進展するにつれ輸出だけでなく現地工場での生産など、海外への直接投資の重要性が高まります。
また輸出や海外直接投資と異なる方法にはライセンシング(ライセンス供与)も考えられます。これら3つの方法のいずれを選択するかで今後の事業戦略に多大な影響を及ぼすことから、企業は慎重な判断を求められます。
●輸出
海外へと製品を輸出するケースには「自社製造製品を輸出する」または「受託企業の製品を代理製造(OEM)し輸出する」の2つのケースが考えられます。自社製造製品を輸出する場合には、流通戦略を同時に計る必要があり、自社の販売網を築くのか、他社の販売網を活用するのか、または現地企業との協業を図るのかなど、あらゆる選択肢から事業戦略を策定していきます。
●海外直接投資
海外直接投資とは、企業が株式取得または工場を建設することで、海外において優位に事業を行うための投資を指しており、外国の企業対して永続的な権益を取得することを目的に実施されます。どこの国(地域)を選択するか、そこで何を重視するか、完全所有にするか合弁か、現地思考か輸出思考かなど、あらゆる選択肢から事業戦略を策定していきます。
●ライセンシング
ライセンシング(実施許諾)とは、著作権を有する特許権者が有償で、第三者に使用を許諾することをさしており、許諾する側をライセンサー、許諾を受ける側をライセンシーと呼びます。また、ブランドやキャラクターなどライセンスの対象をプロパティと呼びます。ライセンシングの活用方法には主に、「商品化」または「プロモーション」の2つのケースが考えられます。例えば商品化の場合、アパレルブランドや日用品メーカーとのコラボレーションが多く行われており、洋服屋や雑貨類、高級ブランド品に至るまであらゆる商品が開発されています。
また、プロモーションの場合、メーカーやコンビニなどの小売店が、キャラクター商品を景品に大々的なプレゼント・キャンペーンを展開するなどが分かりやすい事例に挙げられます。ライセンシングはあくまでも実施権の使用許諾であり、特許権の移転とはならないことを留意しなければなりません。
グローバル企業の戦略マネジメント
グローバル戦略は大きく2つの戦略に分けられます。ひとつが、進出先の市場や文化を都度調査し、最適化されたマーケティング戦略を展開する「現地適応」。もうひとつが、生産効率やマーケティング戦略の標準化を図り、グローバル展開による規模の経済やブランドの統一を図る「統合」です。あらゆる業界で熾烈なシェア争いが繰り広げられる現代においては、現地適応をベースにグローバル統合を図る中間的なモデルが提唱されています。
バートレットとゴシャールの4類型
バートレットとゴシャールの4類型とは、クリストファー・バートレットとスマントラー・ゴシャールの共同研究による多国籍企業のモデル類型を指しています。バートレットとゴシャールは、日米欧9つのグローバル企業・250名以上のマネジャーに聞き取り調査を行い、「①グローバル組織」「②マルチナショナル組織」「③インターナショナル組織」の3つの経営モデルを発見。その上で、これら3モデルの特徴を全て備え、ローカル市場のニーズを組み上げるための現地拠点を有した新たなモデル「④トランスナショナル組織」が必要だと解きました。

①グローバル組織
グローバル組織に属する経営モデルは、世界の市場を単一であると見て、経営資源と権限を本社に集中します。そのため、海外子会社の権限は極めて制限されます。結果、グローバル統合度が高く、ローカル適応度が低いタイプとなり、各国市場に標準化された商品を展開していきます。
集中的大量生産で規模の経済によるスケールメリットを生み出し、コスト優位性から新市場への販売販売チャネル獲得を狙います。
②マルチナショナル組織
マルチナショナル組織に属する経営モデルは、各国・地域ごとに市場やニーズに対応すべく、各国・地域の子会社が独立的に事業を行います。結果、グローバル統合度が低く、ローカル適応度が高いタイプとなり、各国市場の違いに対応した事業・商品を展開していきます。
分権的に経営される強力な現地子会社の集合体として運営され、各国ごとに優位性を追求する戦略で市場シェア獲得を狙います。
③︎インターナショナル組織
インターナショナル組織に属する経営モデルは、グローバル組織とマルチナショナル組織の中間に位置付けられるタイプで、グローバル組織よりは海外資源や意思決定権を海外子会社に委任しますが、重要な経営資源と意思決定権は親会社に集中されます。技術重視に徹し、知識と専門的能力を後進地域に移転・共有し適応させることで、売上向上とコスト削減を図りシェアの獲得を図ります。
また、グローバル規模で学習を繰り返すことで、常に改善を図ります。
④︎トランスナショナル組織
トランスナショナル組織に属する経営モデルは、グローバル統合の効率性とローカル適応の競争優位性の両立を目指し、各子会社に独自の専門的能力が構築されるよう経営資源が分配され、自立化を進めていきます。親会社と子会社、さらに子会社間での双方的な連携が計られ、親会社はそれら取り組みの調整や統制を図ります。
パールミュッターのEPRGプロフィール
企業のグローバル化の発展段階を示すモデルとして、パールミュッターはEPRGプロフィールという4つの分類を提唱しています。EPRGプロフィールの分類には、「①本国志向型(Ethnocentric)」「②現地志向型(Polycentric)」「③地域志向型(Regiocentric)」「④世界志向型(Geocentric)」があり、その頭文字を取ってEPRGプロフィールとしています。
EPRGプロフィールは、前記したバートレットとゴシャールの4類型と類似のコンセプトを有する部分も多くあり、いずれも「現地適応」と「統合」がポイントであることを説いています。
①本国志向型(Ethnocentric)
経営資源と権限をすべて本社(本国)に集中し、現地でのローカル人材は登用せず、本社がすべての意思決定をする志向にある企業。集中的大量生産で規模の経済によるスケールメリットを生み出し、コスト優位性から新市場への販売販売チャネル獲得を狙います。バートレットとゴシャールの4類型でいうグローバル組織と類似したコンセプトを有します。
②現地志向型(Polycentric)
経営資源と権限を現地子会社に移譲し、独立的に事業を行う志向にある企業。各国ごとに優位性を追求する戦略で市場シェア獲得を狙います。バートレットとゴシャールの4類型でいうマルチナショナル組織と類似したコンセプトを有します。
③地域志向型(Regiocentric)
欧州圏、アジア圏といった地域単位に経営資源と権限を移譲し、各地域での現地適応性と規模の経済によるスケールメリットを生み出すことで、市場シェア獲得を目指す志向にある企業。本国志向型と現地志向型のメリットをバランスよく得ることのできる戦略です。
④世界志向型(Geocentric)
経営資源をグローバルに共有し、本国と外国の関連会社が全社的に統合された理想形を具現化する志向にある企業。ディズニーランドやユニバーサルスタジオなどが代表的な例として挙げられます。
BOP市場に対するアプローチ
BOP(Base of the Pyramid)市場とは、所得階層別人口ピラミッドの最底辺に位置する市場を指しており、途上国の低所得者層を対象に約40億人規模の人口が存在すると言われています。BOP市場は、競争の少ないブルーオーシャン市場と捉えることもできれば、中長期を見据えた成長市場、または本業を通じたCSR活動の場と捉える企業も存在します。
BOP市場は、成長の可能性を秘めた大きなフィールドである一方、計り知れないリスクの潜んだ市場であるとも言えることから、日本企業のBOP市場への本格的な進出は慎重な姿勢が取られているのが現状です。BOP市場でのビジネスモデルの多くが、低価格・定利益率・大量販売という薄利多売のビジネスモデルであり、多くの企業が苦戦を強いられていることから、BOP市場で成功を収めるためには、利益率の改善と価格の引き上げが重要なポイントであると言われています。
それらを成功させるためには、現地適応しながらも規模の経済を傍受する「トランスナショナル組織」である必要があり、ブランド認知・拡大に向けた「先行投資」の観点や、「CSR活動」の観点も併せ持つ必要があると言えます。BOP市場へのアプローチには、「ビジネスと社会貢献活動の両立」という考え方が不可欠なのです。

ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《関連するブランディング実績》
Prev
企業間取引と垂直統合
Next
継続企業と最終目標