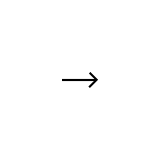126
経営計画とマネジメント
計画することで、ブレなくランニングする。
短期・中期・長期経営計画と、バランス・スコアカード4つの視点。
経営計画とマネジメント
企業は、ビジョン(目標・構想・未来像)やミッション(使命・目的・任務)に基づき策定された戦略のもと、具体的な戦術を持って経営目標を達成していきますが、人・物・金・情報などの経営資源をどのように活用していくかを、経営計画として示すことが肝要です。そして経営計画の実施段階では、PDSからなるマネジメントサイクルに基づき、計画、実行、統制を繰り返し実施することが大切です。
また企業は、経営計画を「長期経営計画」、「中期経営計画」、「短期経営計画」の3段階で策定し、戦略・戦術策定に向けた基本方針を打ち出し、すべての従業員と共有することも怠ってはなりません。
●長期経営計画
ビジョンの実現に向け、5年から10年の長期的視点で策定される経営計画が長期経営計画です。企業の経営戦略を具体化するものであり、ドメインの方向づけとなる重要な計画であると言えます。長期経営計画は、短期計画を統制する役割を担い、短期経営計画実施の結果に基づいて改正され、改正された長期経営計画に基づき、新たな短期経営計画が立てられるなど、積極的に活用されていきます。
●中期経営計画
長期経営計画に基づき策定され、長期経営計画よりもさらに具体的な方針などがまとめられます。3年から5年程度で実施する計画となり、売上高や社員数、企業規模などが具体的な目標値として設定されます。多くの企業で策定され、企業運営の方針として最も活用されているのが、この中期経営計画だと言えます。中期経営計画は、日常業務において従業員の判断基準ともなる重要な役割を果たすことから、現実を見据え策定していくことが肝要です。
●短期経営計画
中期経営計画に基づき策定され、中期経営計画よりもさらに具体的な実行計画などがまとめられます。半年から1年以内の短期間で実行されるための計画であるため、短期間でPDSが行われていきます。長期経営計画において、商品・サービスなど大きな括りで区分していたものを、短期経営計画ではより詳細に、商品毎に計画を策定していきます。また、中期経営計画において年単位で計画策定していたものを、短期経営計画では月単位で数値化していくなどが考えられます。
※PDSとは 「Plan:計画」、「Do:実施」、「See:統制」の頭文字をとったマネジメントサイクルです。明確に策定された企業の経営目標に対し、計画・実施・統制を繰り返し行うことで、目標達成へとつなげていきます。
・Plan:計画/将来における企業の目標を達成するための活動計画を立案する
・Do:実行/Planに基づき組織を構成し、指揮・命令の下に計画を遂行する
・See:統制/実行過程が計画に適合しているかどうかチェックし実現に導く
不測の事態に対応するクライシスマネジメント(危機管理)
企業は、組織の存続そのものや、事業の継続を脅かすような不測の事態をあらかじめ想定し、被害を最小限に止めるための行動方針や計画等をあらかじめ策定することで、危機管理体制を整えなくてはなりません。それを「クライシスマネメント(危機管理)」と言います。
ここで指す不測の自体は企業・組織により様々ですが、一般的には「滅多に発生しないが、ひとたび発生した場合に組織にもたらすインパクトが大きいもの」とされています。例として、地震・台風などの天災、風評、戦争などが上げられます。
●コンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)
事件・事故・災害など、万が一に発生するかもしれない不測の事態を想定し、その影響や被害を最小限に止めるために、予め定める対応策や行動手順がコンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)です。コンティンジェンシー・プランは、リスク発生時の被害の大きさや、その確率などを加味して策定されますが、主には、緊急時における行動指針や行動計画、お客様やメディアへの対応方針、業務や機能の継続方法ならびに復旧作業の優先順位などが策定されます。
その他、代替設備の用意や代替業者の連絡先など、万が一に備えたあらゆる対策を策定することで不測の事態に備えます。
●BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、事件・事故・災害などの緊急事態が発生した際に、企業がその影響や被害を最小限に止め、事業の継続や復旧を図るための計画を指しています。コンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)と類似した意味合いを持ちますが、コンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)は緊急時の初期対応策について力点を置き、BCPは事業継続における対応策について力点を置き定めていきます。
また近年では、BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント)という考え方も多く聞かれるようになりました。BCMは、企業・組織における不測の事態を定期的に見直し、運用していくマネジメントとされており、近年の気象変化や、外部環境の急激な変化にBCMは不可欠な対策だとされています。
●ローリング・プラン(Rolling Planning)
ローリング・プラン(Rolling Planning)とは、不測の事態に対応するコンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)やBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは異なり、計画を練り直しながら前進させることを指しています。企業・組織において、策定した短期経営計画や中期経営計画などを定期的に見直し、環境に適合させていく方法です。一旦策定された中期計画を固定する固定的計画法と対照的な方法であり、定期的に見直しを図ることで計画の実現性を高めていきます。
その一方、見直しされることを前提とするため、努力目標としての機能は低下すると言えます。
経営計画実行を業績評価するバランス・スコアカード
バランス・スコアカードは、戦略経営のためのマネジメントシステムであり、企業が経営計画を実行した際の評価指標です。企業が持つ「財務」「業務プロセス」「学習と成長」「顧客」の4つの視点から業績評価指標を可視化することで、適切に社内のPDCAを適切に行うことができます。
これにより、経営課題として多く挙げられる人材育成や顧客満足度の向上、売上・利益の向上、財務体質の改善などの効果も期待できます。

バランス・スコアカードの4つの視点
バランス・スコアカードは、企業が持つ「財務」「業務プロセス」「学習と成長」「顧客」の4つの視点で構成されており、「財務の視点」では株主をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の期待に応えるために、財務的業績の向上から目標達成を目指します。その財務的業績の向上には「顧客の視点」が不可欠であり、顧客満足度の向上を図らなくてはなりません。
また、顧客満足度の向上には、その「業務プロセス」が大切な役割を果たし、顧客満足度の高める業務プロセスには「学習と成長」が不可欠となります。
このようにバランス・スコアカードにおける4つの視点は、それぞれに深い関連性があり、そのどれが欠けても企業の成長、業績の向上は図れないと言っても過言ではありません。
①財務の視点
バランス・スコアカードにおける「財務の視点」とは、財務的業績の向上を目的に、株主をはじめとするステークホルダー(利害関係社)に対してどのように行動すべきかを可視化するものです。KPI(具体的指標)として、売上高、営業利益、EVA(経済的付加価値)、ROE(株主資本利益率)、キャッシュフローなどが挙げられます。
財務の視点は、事業のライフサイクルを念頭に、成長期(投資段階)の財務的目標、維持期(利益の最大化を図る段階)の財務的目標、収穫期(資金回収の段階)の財務的目標と、事業の段階に応じて策定することが肝要です。
②顧客の視点
バランス・スコアカードにおける「顧客の視点」とは、顧客が商品購入やサービス利用を継続してもらうための行動を可視化するものです。顧客の視点は、顧客の立場からの視点(顧客志向指標)と企業の立場からの視点(顧客収益性指標)の2軸で構成されています。
➡︎顧客の立場からの視点(顧客志向指標)
顧客の立場からの視点(顧客志向指標)では、マーケティングの観点で顧客志向を捉え、いかにして自社製品・サービスの価値を高め、ブランドイメージの向上から顧客満足度の向上を図るかを重視した戦略・戦術を策定していきます。
また、ブランド・エクイティ(ブランド価値)を高め、ブランド・ロイヤルティ(ブランドへの忠誠度)を高めるためのプラン策定を行います。
➡企業の立場からの視点(顧客収益性指標)
一方、企業の立場からの視点(顧客収益性指標)では、マーケティングの観点で顧客収益性を捉え、いかにして企業の収益性を高めるかを重視した戦略・戦術を策定していきます。
具体的には、いち製品あたりの収益性やコミュニケーション費用、そして顧客一人あたりの単価を高めるためのプラン策定を行います。
③業務プロセスの視点
バランス・スコアカードにおける「業務プロセスの視点」とは、企業のビジョンやミッションの達成を目標に、競合他社よりも優れた業務プロセスの確立に向け、対応能力備えていくための行動を可視化するものです。業務プロセスの視点では、3つの業務プロセスを重視していきます。
(1)イノベーション・プロセス 市場・顧客ニーズに合致した製品・サービスを企画・開発するプロセス。
(2)オペレーション・プロセス 製品・サービスの充足に向け、生産・販売など提供を行うプロセス。
(3)アフタサービス 製品・サービス提供後のアフターフォローを行うプロセス。
業務プロセスの視点は、財務的な成功を収めるために、どのような製品を企画・開発・設計・生産し、どのようなサービスを提供するべきか、という戦略実行の視点からそのプロセスを可視化して行くことが大切です。KPI(具体的指標)として主に、顧客処理時間、インターネット取引・顧客比率、生産リードタイム、原価率、棚卸し資産回転率、不良品の発生率などの業績評価指標が用いられます。
④学習と成長の視点
バランス・スコアカードにおける「学習と成長の視点」とは、短期間での業績向上を目的とするものではなく、中長期的な視点で組織の活性化や人材育成などを計画し、学習能力の向上に向けどのように行動すべきかを可視化するものです。学習と成長の視点は、3つに分類することができます。
(1)社員の意識 労働環境やモラル対策など、自社が社員に選ばれる企業であるかを分析し、社員の意識改革を行うなど対策を策定します。
(2)能力開発 社員の能力向上を目的に、既存社員の持つ能力の開花に向けた対策や、新たな能力開発に必要な対策を策定します。
(3)ナレッジマネジメント 企業や個人が持つアイデアやノウハウの共有・結合を行い、生産性の向上に結びつけます。
学習と成長の視点は、KPI(具体的指標)として主に、リーダーシップ指標、モチベーション指標、資格習得数、年間教育・訓練時間、女性管理職数、入社希望者数、エンパワーメント指数、社員定着率、従業員の満足度などの業績評価指標が用いられます。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《関連するブランディング実績》
Prev
戦略策定の基本プロセス
Next
企業の活動領域を定めるドメイン