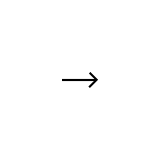125
戦略策定の基本プロセス
発進するときは、正しく発信する。
ビジョン・ミッションの策定と、フレームワークの活用。
戦略策定の基本プロセス
企業は、経営理念に基づきビジョン(目標・構想・未来像)の実現に向け、ミッション(使命・目的・任務)を果たして行きますが、どのような方法でミッションを果たしていくかには、企業戦略の策定が重要な要素となります。
めまぐるしく環境が変化する現代において、ライバル(競合他社)に対する持続的な自社優位性を築く必要があるのはもちろん、限られた資源を最大限に有効活用し、5W1H(いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How))を明確に定めるなど、何に注力していくかの方針が不可欠であるからに他なりません。
経営理念、ビジョン、企業戦略には階層があり、ピラミッドの頂点にあたる上位概念から順次決定して行くことで、理に叶う戦略策定を行うことが可能となります。

●ビジョンとは
企業戦略の策定に不可欠な「ビジョン」や「ミッション」ですが、その意味合いは似て異なるものであると言えます。
まず「ビジョン」とは、直訳すると「目標、構想、未来像」などと訳されます。これを企業のビジョンとした場合には
・組織として目指す方向性
・組織としてありたい姿
・組織が目指す未来の目的地
と置き換えることができます。
具体的に何をするかを策定するものではなく、「将来こうありたい」など、企業としての目標を明確に示すことで、ステークホルダーに自社の存在意義を明確に伝えていくことができます。
これにより、ビジョンに共感する投資家や従業員が企業に集い、ひとつの目標を目指し企業運営を果たしていくことができるようになります。
●ミッションとは
次に「ミッション」とは、直訳すると「使命、目的、役割、任務、存在意義」などと訳されます。
ビジョンの達成に向け、企業はミッションを果たしていきますが、企業がその経営を通じて、何を成し遂げたいかを明文化したもので、このミッションがあることではじめて、ビジョンを明確に掲げることができるとも言えます。
また、ミッションを全従業員が深く理解することで「なぜこの業務を行うのか」に理解・納得が得られることから、ミッションの策定は企業経営に不可欠な基礎的な考えであると言えます。
戦略策定のギャップ
経営者の思いから策定される、ビジョン(目標・構想・未来像)やミッション(使命・目的・任務)から企業戦略を実行していくと、実務において少なからず現実とのギャップが生じてきます。企業は戦略策定にあたり、理想と現実とのギャップを埋めていくために、自社はもちろん、競合他社や市場を深く理解しなければなりません。その際、多く活用されるフレームワークが「3C分析」や「SWOT分析」です。
経営理念やビジョンを前提として、「外部環境分析:環境の与える機会と脅威」や「内部環境分析:自社の強みと弱み」の分析を行い、業界における自社のポジショニングや、自社が市場とするターゲット市場のセグメンテーションを行うことではじめて、現実的な経営戦略を策定することができるようになります。
また、戦略から具体的な戦術に落とし込み実施した際は、PDCA(課題抽出から改善)を繰り返し行い、戦略・戦術の見直しを常に行っていかなければなりません。
●3C分析
「Customer:市場・顧客」、「Competitor:競合」、「Company:自社」の頭文字をとった3つの視点で分析を行うため「3C分析(さんしーぶんせき)」と呼ばれます。3C分析を行うと外部要因である市場・顧客(求職者)と内部要因である自社の関係性を把握することができるため、求職者と競合企業に対し、どのように対応すべきかが明確化されます。
この3C分析を後述のSWOT分析と合わせて活用することで、顧客と競合に対しどのように自社の強みを活かすことができ、どのような弱みを克服すべきかの可視化が可能です。ターゲット市場の価値観やニーズを分析し、同時に自社と競合の状況を分析することで、事業を成功へ導くためのヒントが見つかります。
●SWOT分析
「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」と4視点の頭文字をとったフレームワークで「SWOT分析(すうぉっとぶんせき)」と呼ばれます。SWOT分析を行うことで自社の強みと弱み、活用可能な機会と排除すべき驚異などの情報を整理することができ、ターゲットと市場にどのように自社の魅力をアピールすべきかのヒントが見つかります。
●PDCA
企業戦略・戦術は、計画(Plan)し実行(Do)に移して終了ではなく、常に課題の洗い出し(Check)を行うことが大切です。計画実行後には必ずフィードバックを行い、次回の活動(Action)に活かして行かなければなりません。
どれだけ綿密に計画しても実行段階で数多くの課題が見つかりますので、戦略・戦術を練るフェーズの内、どの点に課題があったのかを明確化することが重要です。目標設定にそもそも誤りがあったのか、手段が適していなかったのか、フォロー不足であるのかなど具体的に考えていくことで、改善点を浮き彫りにし、改善施策の実行へとつなげていきます。そして、課題の洗い出しは、データを基に定量的に考察することが重要です。
課題の洗い出しを終えたら、実行メンバーで改善施策について検討します。課題と改善施策のアイデアはメンバー間で共有し、戦略・戦術の改善案の立案時に課題を潰した形で策定します。このようなPDCAの繰り返しが効果的な戦略の策定、戦術の実行へとつながります。
分析麻痺症候群の危険性
近年、経営に数値的な解釈を加え、KGI(Key Goal Indicator)、KPI(Key Performance Indicator)などで客観的な分析を行うことも一般的となってきましたが、一方で数値化することや分析することばかりに意識が集中し、現場の実情や現場からの声を軽視してしまうことや、現場の状況を感じ取る能力が劣ってしまうケースが問題視されています。これを「分析麻痺症候群」と言います。
分析麻痺症候群に陥ると、分析すること自体が目的になってしまうマーケティング分析や、使い道のないデータ分析を繰り返し行い、結果、時間や費用のロスを招くばかりでなく、現場と本社スタッフの間に不信感が生じるなどの問題が発生します。
大切なのは、分析はPDCAの一部であることを念頭に置き、現場の実情や現場の声を踏まえ、分析からトライ&エラーまでをスピード感を持って積み重ねることに他なりません。ゴールを見失わないこと。これが重要なポイントです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《関連するブランディング実績》
Next
経営計画とマネジメント