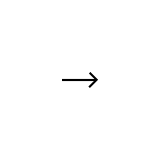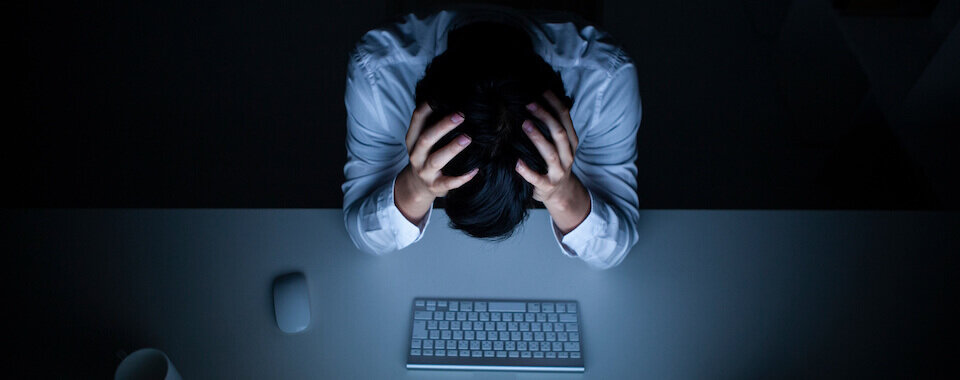
168
社員の離職リスクを防ぐ「心理的安全性」と仕組みづくりの実践法
心理的安全性でつくる強い組織
離職前に抱きやすい「3つの不安」と、その解消につながる仕組みづくりをご紹介します。
優秀な社員が辞める前に抱える「3つの不安」とは?
「信頼していた優秀な社員の突然の退職」そんな経験をした経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。優秀な社員が離職する理由は、必ずしも「給与」や「待遇」だけではありません。多くの場合、それ以上に大きな要因となるのが「心の不安」です。
特に人材不足が深刻化する今、優秀社員の離職は企業にとって大きな痛手となります。そして優秀な人材ほど環境に敏感で、「もうダメだ」と感じた瞬間に素早く動くものです。待遇が良くても、次の「3つの不安」が解消されなければ、彼らは迷いなく次のステージへ進んでしまいます。ここでは、優秀社員が離職前に抱きやすい3つの不安をご紹介します。
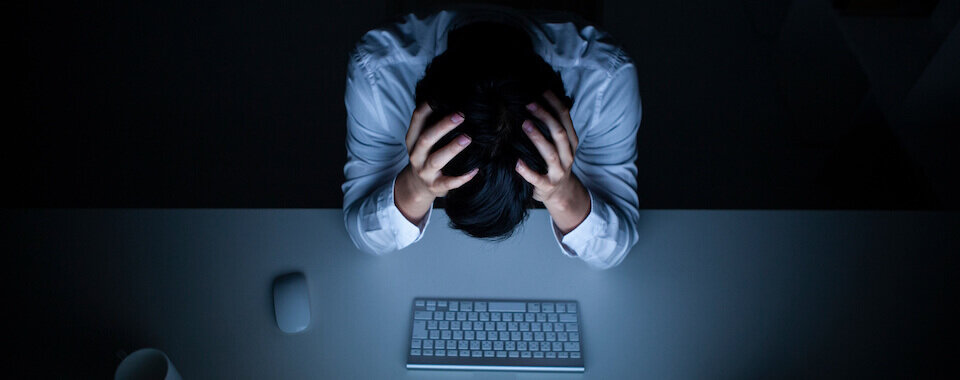
【不安①】ここにいて大丈夫?
社員が「自分はこの組織にとって本当に必要な存在なのだろうか」と感じ始めると、不安が徐々に募っていきます。役割や期待されていることが曖昧で、自分の仕事が会社やチームにどう貢献しているのかが実感できない状態が続くと、「自分がここにいる意味」を見失いがちに。
この状態が長引けば、組織に対する帰属意識やモチベーションが低下し、いずれ離職の選択肢が現実味を帯びてきます。
【不安②】このままで大丈夫?
今の仕事が自身の成長につながっている実感が持てないと、キャリア停滞への不安が生まれます。日々の業務がルーチン化し、スキルや知識の向上を感じられなかったり、新しいチャレンジや学びの機会が得られなかったりすると、「このままここにいても将来が見えない」「市場価値が下がってしまうのではないか」と危機感を抱くようになります。
優秀な社員ほど成長意欲が高いため、この不安が転職を決意する大きな引き金となります。
【不安③】この会社、大丈夫?
経営方針やビジョンが社員に十分に共有されておらず、会社の将来像が見えにくい状態では、組織や経営への信頼が揺らぎます。「この先、会社はどこに向かうのか」「経営層はどんな考えで意思決定をしているのか」が見えなければ、社員は不安を抱き、自分のキャリアを預け続けることに疑問を持つようになります。
特に優秀な社員ほど将来の展望に敏感なため、会社の安定性や成長性に対して疑念が生じれば、次のキャリアへの一歩を踏み出す判断材料となってしまうのです。
社員の不安は“仕組み”で解消する

優秀な社員が抱く3つの不安は、単なる声がけや個別対応だけでは根本的な解決に至りません。「ここなら安心して働き続けられる」「ここで成長していける」と社員自らが納得できる状態をつくるには、 “仕組み”としての整備が不可欠です。それぞれの不安に対して、次のような取り組みが有効です。
【解決策①】心の報酬を与える
「ここにいて大丈夫?」という不安を解消するには、社員が「自分はこの組織に必要とされている」と実感できる環境づくりが大切です。また、日常の中で、愛情・承認・感謝の言葉や態度を意識的に伝えることが大切です。
さらには成果だけでなく、社員一人ひとりの存在そのものに価値を見出していることを示す場(1on1/表彰/社内コミュニケーション)を整えることも大切な取り組みのひとつです。社員が「自分は意味のある存在だ」と実感することで、帰属意識と定着意欲が自然と高まります。
【解決策②】成長機会を提供する
「このままで大丈夫?」という不安を抱かせないためには、成長意欲の高い社員に適切な負荷のある仕事や新たなチャレンジの機会を意識的に提供することが重要です。
「ここにいればもっと成長できる」「次に挑戦すべき目標が明確だ」と社員が感じられるよう、キャリアパスやスキルマップを整備することも効果的です。学びと挑戦の場があることで、優秀な社員は自身の成長を実感し、組織への貢献意欲も一層高まっていきます。
【解決策③】経営の意思と未来像を見せる
「この会社、大丈夫?」という不安を解消するには、社員が安心して働ける環境づくりが欠かせません。そのために大切なのは、経営者自身が会社の考えや方向性をわかりやすく、継続的に発信していくことです。
ビジョンや方針を一方的に示すだけでなく、なぜそう考えるのか、どんな未来を社員とともに築きたいのかを、日常のコミュニケーションの中で語りかけましょう。透明性のある意思決定と会社の成長ストーリーの共有が、社員との信頼関係と安心感を育てていきます。
こうした仕組みを整えていくことで、社員は「ここでなら自分の価値を発揮できる」と実感し、組織の中で前向きに成長していくいことができます。結果、優秀な社員が定着し、活躍し続けることのできる強い組織文化が生まれていきます。
経営者・管理職が押さえておくべき「心理的安全性」の作り方

社員が安心して意見を出し合い、挑戦し、失敗から学べる組織づくりに欠かせないのが「心理的安全性」です。心理的安全性とは、「この場で自分の意見を言っても否定されない」「自分らしく働ける」と感じられる状態のこと。
社員が安心して自己表現できる職場環境は、チームの創造性やパフォーマンス向上、そして優秀な人材の定着にも直結します。経営者や管理職が意識的に整えていくことが、これからの強い組織づくりの不可欠な要素となります。
1.率直な意見交換ができる「場」をつくる
社員が自由に発言できる環境がなければ、率直な意見や建設的な提案は生まれません。上司と部下の1on1や、チームミーティングなどの場で「意見を言っても否定されない」という空気感を醸成することが大切です。
心理的安全性が高まることで、社員は安心して自分の考えを伝えられるようになり、組織に前向きな対話が生まれます。
2.ミスや失敗を「学び」として共有する文化
社員が「失敗したら責められる」と感じてしまうと、チャレンジ精神が失われていきます。ミスや失敗は責めるのではなく、そこから何を学び、どう活かしていくかという「学びの視点」に転換する文化が重要です。
こうした文化が浸透すれば、社員は失敗を恐れず挑戦できるようになり、組織全体の成長スピードも高まります。
3.多様な意見や価値観を歓迎する姿勢
役職やキャリア、年齢に関係なく、多様な意見や価値観を受け入れる姿勢が心理的安全性の土台になります。特定の声だけが尊重されるのではなく、どんな立場の社員でも自分の視点が歓迎されると感じられることで、組織はより柔軟で創造的な場になります。
多様な視点が活かされる組織は、変化にも強く、イノベーションが生まれやすい環境になります。
4.上司の「傾聴」と「共感」スキルを高める
上司が一方的に指示や評価をするだけでは、社員の本音は引き出せません。相手の話を丁寧に聴き、共感し、理解しようとする姿勢を持つことで、信頼関係が築かれます。
部下の意見や気持ちに寄り添ったコミュニケーションを心がけることで、心理的安全性が高まり、チームの一体感も強まります。
5.経営ビジョンと価値観を「日々の言葉」で繰り返し発信する
会社のビジョンや価値観は、掲示物や一度きりの説明だけでは浸透しません。経営者や管理職が日々の会話や社内のさまざまな場面で一貫したメッセージとして発信し続けることが重要です。
社員が会社の目指す方向性を理解し、自分の仕事とのつながりを感じられることで、安心して主体的に働ける組織づくりへとつながります。
まとめ:社員の離職リスクを防ぐ「心理的安全性」と仕組みづくりの実践法
いかがでしたでしょうか?優秀な社員が辞めない組織をつくるためには、心理的安全性の高い職場づくりと、社員の「3つの不安」を解消するための仕組みづくりが不可欠です。
日々のコミュニケーションや制度、文化を意識的に整えていくことで、社員が「ここでなら自分の力を発揮できる」と実感し、安心して成長し続けられる環境が生まれます。結果として、離職リスクを防ぎ、活躍する人材が育つ強い組織へとつながっていきます。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。