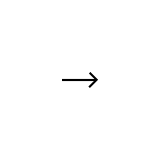167
マネジメントをしなくても成果が出る「自律型の組織」とは
成果を生む「自律型組織」のつくり方
社員の自律性と組織の一体感を育て、マネジメントに頼らず成果を生み出すための実践ポイントを解説します。
社員のセルフマネジメント力を高め、一体感あるチームをつくる
現代のビジネス環境は、変化のスピードがこれまでになく早く、多様化が進んでいます。そんな中、従来の「管理型マネジメント」だけでは、現場での柔軟な対応力やスピーディな意思決定が追いつかなくなっています。こうした背景から注目されているのが、「自律型の組織」です。
これは、管理職やリーダーが細かく業務を管理しなくても、社員一人ひとりが自ら考え、判断し、責任をもって成果を生み出す組織形態のこと。社員自身がセルフマネジメント力を高め、組織のビジョンや目的に向かって自律的に動くことで、イノベーションや高いパフォーマンスが生まれやすくなります。
しかし、「放任」することと「自律を促す」ことはまったく違います。社員の意識を変え、行動を変え、組織全体が一体感をもって動くためには、いくつかの仕掛けと工夫が必要です。ここでは「自律型の組織」を作るための考え方や実践のステップをご紹介します。
マネジメントに頼らず成果を生む「自律型組織」のつくり方

「自律型の組織」は、「目標」と「信頼」をベースに社員が動きます。上からの細かな指示ではなく、社員自身が目標や役割を理解し、自ら意思決定しながら仕事を進める文化が根づいているのが特徴です。
一方、ただ「自由にやっていい」と伝えても、自律は生まれません。必要なのは、社員一人ひとりの「目的意識」と「セルフマネジメント力」を育む仕掛け作りです。
社員のセルフマネジメント力を鍛えるポイント

「自律型の組織」を実現するための土台となるのが、社員一人ひとりのセルフマネジメント力です。セルフマネジメント力とは、自分の目標や役割を理解し、計画的に業務を遂行しながら、自らの行動や成果を振り返り改善していく力を指します。この力が育つことで、上司や管理職が細かく指示を出さなくても、社員は自ら考えて動けるようになります。
ここでは、社員の自律性を高めるために欠かせない「目的・目標の明確化」「成長意欲を引き出す」「自己管理力の強化」という3つの観点から、具体的な育成のポイントをご紹介します。
1.目的・目標の明確化
自律的に動くための第一歩は、「なぜこの仕事をするのか」「何を目指しているのか」という目的や目標を社員自身がしっかり理解し、腹落ちしていることです。上司から与えられた目標をただ「こなす」のではなく、自分の言葉で語れる状態になることで、仕事への主体性が高まり、より良い成果を目指す意識が自然と芽生えます。
そのためには、単に業務指示を出すだけでなく、背景や意義を丁寧に共有し、社員が納得して行動できるような対話が欠かせません。
2.成長意欲を引き出す
社員が自ら挑戦し、前向きに行動を起こすためには、失敗を恐れずチャレンジできる環境が必要です。そのために重要なのが「心理的安全性」です。たとえミスや失敗があっても責められることなく、それを学びや成長の機会ととらえられる組織文化があることで、社員の挑戦意欲は高まります。
さらに、自分の成長が組織に貢献している実感が得られることも意欲向上につながります。成長の過程を上司や仲間が承認し、称賛する場をつくることも効果的です。
3.自己管理力の強化
自律的な社員には「自分の仕事を自分で管理できる力」が求められます。そのためには、進捗状況や課題を自ら把握し、必要に応じて軌道修正する習慣を持つことが重要です。また、状況に応じて自分で目標を見直したり、行動計画を調整したりする柔軟性も必要です。
この自己管理力を育むには、上司が一方的に管理するのではなく、社員自身が目標設定や振り返りに主体的に取り組める仕組みや機会を用意する施策が効果的です。たとえば、定期的な1on1やセルフチェックリストの活用が役立ちます。
組織の一体感を醸成する「3つの仕掛け」と実施ステップ
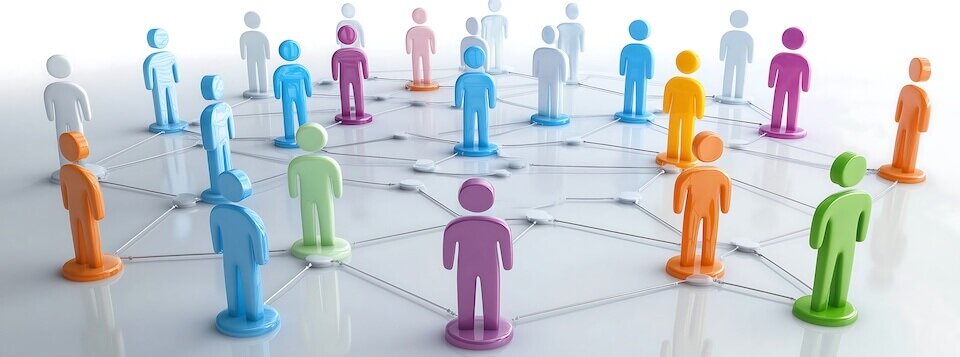
「自律型の組織」を成功させるには、単に個々が自由に動くだけではなく、組織全体としての一体感が重要になります。共通の方向性や価値観を持ち、メンバー同士が信頼し合うことで、自律的な行動が組織の成果としてまとまり、より大きな力となります。その一体感を醸成するために効果的なのが、次の3つの仕掛けです。
1.理念・ビジョンの共有と対話
理念やビジョンは、社員が「なぜこの組織で働くのか」「何を目指しているのか」を共有するための軸となります。しかし、単に掲示したり資料で配布するだけでは形骸化しがちです。
重要なのは、理念やビジョンについて対話する場をつくり、社員一人ひとりが自分ごととして捉えられるようにすること。ワークショップや1on1、全社会議などで理念について語り合う機会を設けることで、社員は組織の目指す方向を深く理解し、自分の役割や貢献の意味を見いだせるようになります。
2.心理的安全性のある関係性作り
社員が自律的に考え、意見を出し合い、行動していくためには、心理的安全性が不可欠です。心理的安全性とは、「このチームでは自分の考えや疑問を自由に発言しても否定されない」「失敗しても学びの機会として受け入れてもらえる」という安心感のことです。この安心感があることで、社員は率直な意見交換や情報共有ができ、チームとしての信頼関係も深まります。
そのために、上司やリーダーはまず率先してオープンなコミュニケーションを心がけ、社員同士でも尊重し合える風土づくりを意識して進めていくことが重要です。
3.成果の可視化と称賛
自律的な行動や成果が組織内で共有され、正当に認められることは、さらなる意欲と連帯感を生み出します。社員の成果や取り組みを見える化し、組織全体で称賛し合う文化をつくることで、自然とポジティブな一体感が生まれます。これは単に業績数値だけではなく、日々の行動や姿勢、仲間への貢献なども含めて称え合うことがポイントです。
定例会議や社内SNS、朝礼・夕礼などの場で成果を共有したり、表彰制度やフィードバックを通じて承認する習慣を取り入れることで、社員は自分の存在意義を感じやすくなり、組織とのつながりも強化されていきます。
以上の3つの仕掛けを段階的に、かつ継続的に実施していくことで、組織全体に一体感が育まれ、社員一人ひとりの自律的な行動がより大きな成果につながっていくでしょう。
既存社員の意識と行動変容を起こす6つのポイント

新たな文化づくりや組織変革においては、「既存社員」の意識や行動変容が大きな鍵を握ります。しかし、長年の価値観や慣習が根づいている場合が多く、一朝一夕で意識改革が進むわけではありません。
そこで効果的なのが、次の6つのポイントを意識した取り組みです。段階的に進めることで、変化への抵抗感を和らげ、行動変容を促すことができます。
1.現状の可視化(今と理想のギャップを見せる)
まず必要なのは、「現状」と「目指す姿(理想)」の間にどれだけのギャップがあるのかを社員自身が正しく認識することです。漠然と「変わらなければならない」と言われても行動にはつながりません。現状の問題点や課題、理想とする組織像を具体的に可視化することで、社員の危機感や改善意欲が生まれます。例えば、アンケートやワークショップを通じて現状分析を行い、その結果を共有するなどが有効です。
2.成功事例の共有(ロールモデルをつくる)
「誰かがすでにうまくやっている」という成功事例が身近にあると、社員は「自分にもできるかもしれない」という希望を持ちやすくなります。そのため、変化を実践して成果を出している社員やチームの事例を積極的に共有しましょう。ロールモデルとなる社員の具体的な行動や工夫を見せることで、変化が現実的なものとして捉えられるようになります。
3.小さな成功体験の積み重ね(成功体験→自信→行動)
大きな変化を一度に求めると、かえって反発や不安を招きます。まずは「できそうなこと」から小さな成功体験を積ませることが大切です。その成功が自信となり、次の行動につながるという好循環を生み出します。たとえば、行動変容を促す際に「まず1日1回チャレンジしてみる」「まず1つの会議で発言してみる」など、ハードルの低い目標から始めると効果的です。
4.対話による納得形成(押し付けではなく対話型)
意識や行動を変えるには、社員自身が「納得」していることが欠かせません。一方的に指示を出すだけでは形だけの対応になりがちです。なぜ変化が必要なのか、その意義をしっかりと伝え、対話を通じて社員の疑問や不安に向き合いましょう。こうした対話型の進め方により、社員は自らの意思で変わろうという気持ちを持ちやすくなります。
5.仕組み化と習慣化(行動が自然と継続する仕組みを作る)
一度行動変容が起きても、継続しなければ定着には至りません。行動が自然に続くように、日常の業務や評価の中に仕組みとして組み込むことが大切です。たとえば、目標設定や評価制度の中に行動変容に関連する項目を盛り込んだり、行動を促すチェックリストやルーティンを設けたりすることで、習慣化を図ることができます。
6.継続的なフィードバック(成長をサポートする)
行動変容には時間がかかります。途中で不安になったり迷いが生じたりする社員も少なくありません。そこで、継続的にフィードバックを行い、成長の過程を丁寧にサポートすることが大切です。定期的な1on1や評価面談などの機会を活用し、変化への取り組みを認めたり励ましたりすることで、社員のモチベーションは維持されやすくなります。
以上の6つのポイントを意識したアプローチを続けることで、既存社員の意識と行動が徐々に変わります。その結果、自律型組織の文化の定着が期待できます。
浸透しない理念やビジョン 4つの要因
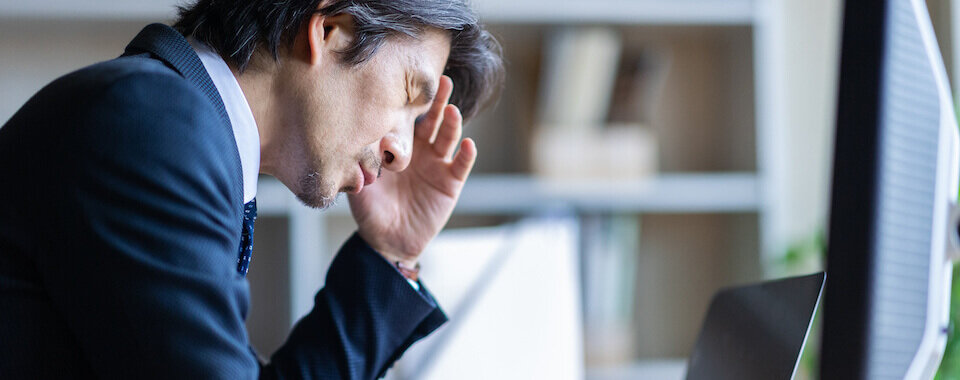
企業の理念やビジョンは、組織全体の価値観や行動の指針となる大切な存在です。しかし実際には、多くの企業で「現場に浸透しない」「形だけになっている」といった課題が見られます。その背景には、いくつかの共通した原因があります。ここでは、理念やビジョンが浸透しない主な4つの要因について解説します。
1.経営層が押しつけがち
理念やビジョンは「上から与えるもの」ではなく、「共に考え、共有し、育てていくもの」です。しかし経営層が一方的に決めた言葉を現場に押しつける形になると、社員は自分ごととして受け止めにくくなり、反発や無関心を生む場合もあります。理念の意義や背景を丁寧に伝え、社員との対話を重ねながら共感を築いていく姿勢が欠かせません。
2.理念と日常業務が乖離している
理念やビジョンが日々の業務や現場の現実とかけ離れていると、「自分たちには関係ないもの」として受け止められてしまいます。理念がどのように日々の行動や判断基準につながるのか、具体的な事例や行動指針とセットで示すことが重要です。現場で実践できる形に落とし込み、社員が業務の中で自然に理念を意識できるようにする工夫が求められます。
3.言葉が抽象的で現場で行動に落とし込めていない
理念やビジョンがあまりに抽象的だと、社員は「どう行動すれば良いのかわからない」と感じがちです。例えば、「お客様第一主義」「挑戦する組織」などの言葉だけでは、日常業務にどう反映させれば良いのかが曖昧になりやすいものです。理念やビジョンに紐づく具体的な行動例や期待される態度を明確にすることで、社員が実際の行動に移しやすくなります。
4.「理解して終わり」で行動につながっていない
理念研修やスローガンの説明会などで一度「理解」はされても、その後、行動や業務にどう反映させるかまでフォローされないケースも多く見受けられます。理念が「知っている」で終わらず、「意識して行動する」までつなげるためには、継続的な働きかけが不可欠です。
日々の業務の中で理念に基づいた行動が求められる場面をつくったり、評価制度や表彰制度と理念を連動させたりすることで、行動への定着が進みます。理念を単なる「額縁の言葉」にせず、社員が自ら行動につなげる工夫が求められます。
理念やビジョンが現場に浸透し、自律的な行動につながるためには、これらの障壁を意識的に取り除き、社員一人ひとりが「自分の仕事にどうつながるのか」を理解できる状況をつくることが大切です。
まとめ:マネジメントをしなくても成果が出る「自律型の組織」とは
いかがでしたでしょうか。マネジメントに頼りきるのではなく、社員一人ひとりが自律的に動き、組織として一体感を持って成果を生み出す「自律型組織」。その実現には、セルフマネジメント力の育成や理念の共有、心理的安全性の醸成といった丁寧な取り組みが不可欠です。
日々の業務や文化づくりを通じて、社員が「自ら考え、動き、貢献したくなる」環境を整えることで、持続的な成長と成果につながっていくはずです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。