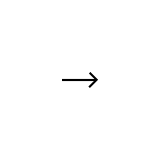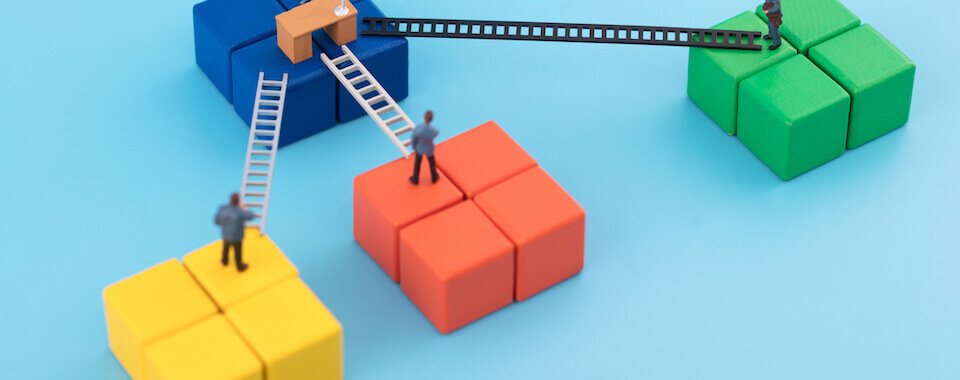
44
ブランディングは「Brand+ing」、継続して初めて力となる。
ブランディングは、一日にして成らず。
開発から運用、中長期的な取り組みが真のブランドをつくります。
そもそも、ブランディングは本当に必要なのか?
ブランディングが必要か否かは、企業の経営方針次第です。
ブランディングを必要とする企業が成し得たいものは「他社との差別化」です。ではなぜ、他社との差別化を図りたいのか。差別化が実現すると、信頼して選ばれる企業、魅力的な製品、安心してご利用頂けるサービスなど、グローバル市場での熾烈な競争が繰り広げられる現代において、「選ばれる要因」が明確化します。
また、国内人口の減少から消費が減退する国内市場においても「国内シェアの獲得」が期待できます。結果、単純な価格競争に巻き込まれることなく、市場で勝ち抜く事業戦略を図ることができます。
一方、超高齢化社会を迎え、少子高齢化問題が取り沙汰される日本において、生産人口の獲得に向けた「採用強化」にもブランディングは好影響をもたらします。ブランドは「愛社精神の醸成」や「仕事のやりがい」にも直結し、「内定辞退率の改善」や「離職率低減・定着率向上」にも寄与します。
企業の成長戦略に不可欠な「売上向上」と「採用強化」。
成長を図る多くの企業にとってブランディングは、避けて通ることのできない必要不可欠な施策であると言えます。
ブランディングを必要としない企業はあるのか?
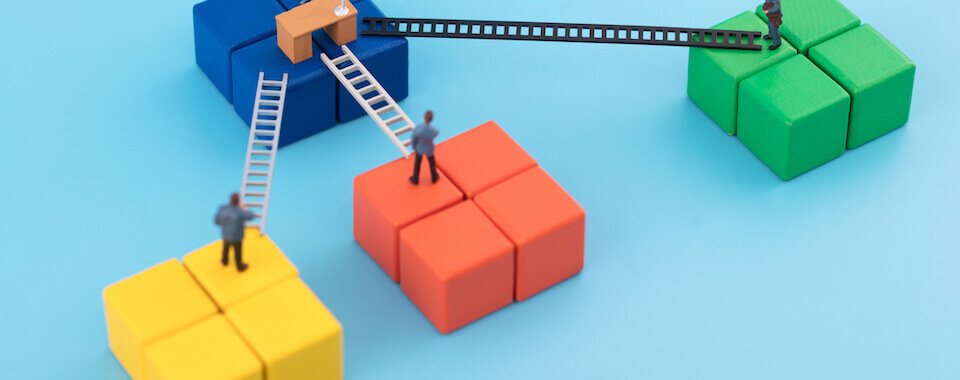
一方、「質より量」の事業戦略を図る企業にとってブランディングは、不要な取り組みかも知れません。あえてブランドを作らないことで、「低価格」を打ち出し、消費者から気軽に選ばれる存在を目指すのも事業戦略のひとつだと言えます。
但し、物やコト溢れる現代において低価格戦略は、熾烈な競争環境にさらされることから、最安値を維持し続けなければ選ばれず、商品であれ、サービスであれ、常に量をこなす必要が生じます。
結果、社員は重労働を強いられ、心身ともに疲弊することが想定されることから、人材獲得及び社員の定着には苦労を伴うことが予想されます。
どのような事業戦略で市場シェアを獲得するか。大切なのは、“どのポジションを目指すか”が明確であることだと言えます。
ブランディングは「Brand+ing」、継続こそ力なり。

これらの要因から、多くの企業でブランディングの取り組みが図られています。
ブランディング=ロゴ、Webサイト、パンフレットなどのデザインを統一すること。と思われている方もいますが、それは表向き見えているブランドの一部でしかありません。
ブランドとは、経営層や社員の言動であり、事業関係者からの信用であり、ブランドへの愛着や想いであり、何より消費者のロイヤルティ(忠誠心)が生み出す企業や商品への信頼の集合体です。
だからこそ、ブランドとしてあるべき姿勢を継続し続けていくことが重要です。ブランディングは英語「Brand+ing」と表すように、継続して初めて企業資産となる、中長期的な取り組みなのです。
◉ブランディングは理念の実践
ブランディングは、企業や組織があるべき姿として掲げる理念を、実際の行動や表現で具体化することです。
つまり、単にロゴやスローガンをつくることではなく、「言っていること」と「やっていること」に一貫性を持ち、その積み重ねによって消費者や社会に形成される「企業の印象や信頼、感情的なつながり」を築くことに他なりません。
◉ブランディングは経営層や社員の言動から
ブランディングは、単なるデザインや広告だけでなく、企業文化や行動そのものに根ざしています。経営層は正しく理念やミッションを実践し、ビジョンの達成に向けた企業経営を行っているか、社員は理念やバリューを正しく理解し、顧客や社会に対し適切なコミュニケーションを図れているか。こうした言動の積み重ねが、社会に愛され、必要とされるブランドをつくります。
◉ブランディングは事業関係者からの信用
ブランディングは、顧客や消費者だけでなく、取引先・株主(投資家)・地域社会・パートナー企業など、事業を取り巻くステークホルダーからの信用を獲得する活動でもあります。
透明性ある経営、社会的責任に取り組む姿勢、一貫したメッセージと行動。これらの積み重ねが事業関係者からの信用を生み、結果として事業の安定と成長につながっていきます。
◉ブランディングはブランドへの愛着や想い
</>ブランディングの目的は、認知度向上や差別化だけでなく、ブランドの感情的価値を育む活動でもあります。消費者や事業関係者が「そのブランドが好き」になり、「信頼できる」と感じる状態をつくり続けることで、ブランドへの愛着(ブランド・エンゲージメント)や共感を持つようになります。
この「好き」「信頼」「愛着」「共感」などの想いが、他のブランドでは代替えできないブランド資産(ブランド・エクイティ)となっていくのです。
◉ブランドは消費者との信頼関係
消費者や顧客にとってブランドは、企業が一方的に築くものではなく、お互いの関係性の中で「育まれるもの」です。そして企業名や商品名などのネーミングやロゴは「約束の象徴」であり、「この企業・この商品なら信頼できる」と消費者や顧客が認識する、安心感の印に他なりません。
品質・サービス・対応・トラブル時の姿勢など、あらゆる側面において「期待に応える」という体験が、消費者や社会との信頼関係を築き、ブランド価値向上へとつながります。
ブランド=高級ではない。ポジショニングで異なるブランド戦略。

一般的に「ブランド」と聞くと、CHANEL、HERMES、Louis Vuitton、Cartierなどのハイブランドが浮かびますが、決してハイブランドだけがブランドではありません。前述する「信用」「愛着」「忠誠心」「信頼」のある企業や商品のすべてが「ブランド」であると言えます。
一例として身近な商品には「ユニクロ」、店舗には「ドン・キホーテ」、サービスには「Amazonや楽天」。これらもブランド要因を備えた、素晴らしいブランドです。
ブランディングではじめに取り組むべき「ブランドの言語化」

いち消費者として市場を見たとき、デザインされたロゴや商品、コミュニケーションデザインなどが浮かびますが、これらブランドデザインの大半は言語化されたブランド像から作り出されています。
企業ブランドであれば、経営理念やMVV。商品ブランドであれば、ブランドコンセプト。ブランドの姿勢を言語化することで、はじめてブランドデザインが形成されていきます。
◉企業ブランドの言語化|企業理念やMVV
企業ブランディングにおける最重要ステップのひとつに「企業理念やMVV(Mission, Vision, Value)の言語化」があります。ブランドの言語化は、企業の存在意義や価値観、目指す姿などを「言葉」により明確に表現することで、すべてのステークホルダーに誤解なく企業のあり方を伝えていくために不可欠な取り組みだと言えます。
ブランドの根幹となるMission(使命)は企業が社会に存在する意義であり、ブランドの方向性を示すVision(将来像)は企業が目指す理想の姿(ありたい姿)です。
また、ブランドの性格や文化を示すValue(価値観)は企業の意思決定や行動の基準となる信念であることから、企業理念やMVVの実践の積み重ねが、企業文化や風土の土台、すなわちブランドをつくると言っても過言ではありません。
◉商品ブランドの言語化|ブランドコンセプト
商品ブランディングにおける最重要ステップのひとつに「ブランドコンセプトの策定」があります。ブランドコンセプトは、“商品やサービスの核”を明文化し、消費者や社会に一貫した提供価値を伝えるメッセージであることから、“商品やサービスの存在価値そのもの”だと言い換えることができます。
ブランドコンセプトの策定、すなわち商品ブランドの言語化は、その商品・サービスが「誰に、どんな価値を、どのように届けるか」を明確に表現することと同義であるため、ブランディングではじめに取り組む施策だと言えます。
いつまでも「愛されるブランド」であるために

市場に必要とされ、社員や事業関係者に愛され、企業にとってかけがえのない経営資源であるブランド。そんなブランドを次世代まで継承していくために、最も大切にしなければならないポイントは「ブランドとしての誠実さ」です。 食品であれば「安心・安全・そして味などに誠実」であること。商品であれば「品質・アフターサービス・サステナビリティなどに誠実」であること。サービスであれば「技術・接遇などに誠実」であること。
お客様はもちろんのこと、社員や事業関係者にもブランドのファンであって頂くために「誠実さ」に取り組み続けることではじめて、「愛されるブランド」に成ることができるのです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。